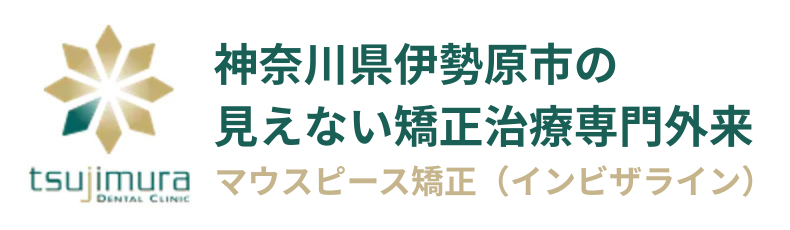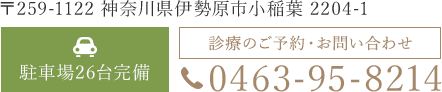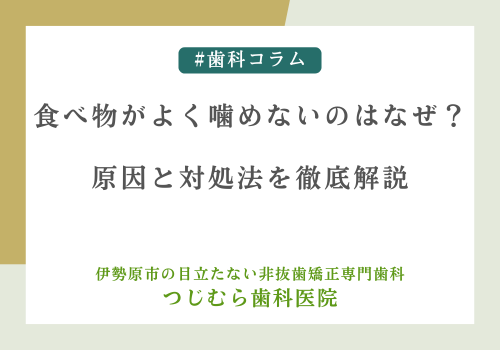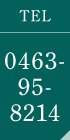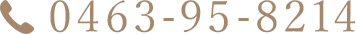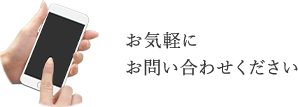こんな症状ありませんか?噛みにくさに気づくきっかけ

「最近、食べにくいと感じることが増えた」「以前より顎が疲れるようになった」――そんなささいな違和感は、身体からの大切なサインかもしれません。噛む力の低下はゆるやかに進行し、気づかぬうちに食事の満足感や健康を脅かしていることもあります。ここでは、噛みにくさに気づくきっかけと、その代表的な症状について解説します。
食事中に感じる違和感
「なんとなく噛みにくい」「前より疲れる」そんな小さな違和感は、体からのサインかもしれません。噛む力の変化は、気づきにくいものですが、食生活や日常の快適さに大きく影響します。まずは、どのような場面で噛みにくさを感じるのか、一緒に確認してみましょう。
「最近、食べづらくなったな」「片側だけで噛んでいるかも…」そんな小さな違和感、見逃していませんか?
噛みにくさは、ある日突然感じるというよりも、じわじわと進行していくことが多いのが特徴です。たとえば、以前は問題なく食べられていたお肉が硬く感じたり、パンやごはんが口の中でまとまらず飲み込みづらかったり。こうした微妙な変化は、噛む力が弱まってきているサインかもしれません。
特に注意が必要なのが、「何となく避けている食材」が出てきたとき。無意識に柔らかいものばかり選ぶようになったり、食べる量そのものが減っていたりする場合は、お口の中の異常を疑ってみるべきです。
噛む力が弱くなったと感じる瞬間
噛む力が落ちてくると、食べものをしっかり細かく砕けず、消化にも影響を及ぼします。また、噛むたびにあごに疲れを感じたり、顎関節がパキッと鳴ったりする方もいます。
「奥歯でしっかり噛みしめられない」「固いせんべいやお漬物が苦手になった」という感覚は、噛む力の低下を示す代表的な兆候です。
また、高齢者だけでなく、働き盛りの大人でもストレスや歯ぎしり、噛み合わせのズレなどで噛む力が落ちていることがあります。日々の生活のなかで、「最近よく食べこぼす」「食事の後にあごが疲れる」といった症状があれば、ぜひ早めに歯科医院にご相談ください。
噛めないことによる生活への影響
実は、「噛めないこと」は、食事の楽しみを奪うだけでなく、全身の健康にも大きく関わってきます。噛めなくなることで栄養バランスが偏ったり、食欲が落ちて体重が減少したり、さらには筋力や免疫力の低下、認知機能の低下にもつながることが知られています。
また、しっかり噛めない状態では、滑舌が悪くなる、表情が乏しくなる、口元がたるむなど、見た目にも変化が現れます。特に高齢者にとっては、オーラルフレイル(口腔機能の低下)への入り口になる可能性もあり、見過ごすことはできません。
「食べること」は健康の土台。噛みにくさに早く気づき、対応することで、将来の健康リスクを大きく減らすことができます。
些細な違和感でも構いませんので、気になる症状があれば、ぜひ一度ご相談ください。
よく噛めない原因はさまざま|まずは口腔内をチェック

噛めない・噛みにくいと感じたとき、その原因は一つではありません。虫歯や歯周病といったトラブルはもちろん、噛み合わせのズレや補綴物の不具合など、多くの要因が重なっているケースもあります。ここでは、よくある3つの原因に絞ってわかりやすく整理し、原因に気づくヒントをご紹介します。
虫歯・歯周病・歯の欠損
「噛みにくい」と感じたとき、まず疑うべきは虫歯や歯周病といった口腔内の病気です。特に虫歯が進行して神経に達してしまうと、噛んだときの痛みで咀嚼を避けるようになってしまい、自然と噛む力が弱まってしまいます。また、歯周病によって歯を支える骨が溶けると、歯がグラグラしたり抜けてしまったりすることもあり、噛む面積そのものが減ってしまいます。
そして、歯を失ったまま放置していると、周囲の歯が傾いたり、噛み合わせが崩れることで全体のバランスが悪くなり、さらに噛めなくなるという悪循環に陥ります。実際、「噛めない」と感じる方の多くが、過去の虫歯治療や抜歯の影響を抱えているケースも少なくありません。
噛み合わせや顎のずれ
もう一つの大きな要因が「噛み合わせ(咬合)」です。上下の歯が正しく接触していない状態、いわゆる咬合不全は、左右のどちらか一方ばかりで噛むクセを生んだり、特定の歯に負担をかけて痛みや疲労感を引き起こします。顎関節に負担がかかることで、あごの違和感や開閉時の痛みを訴える方もいます。
また、過去の歯科治療や事故・ケガ、あるいは成長期の噛み合わせのズレが影響して、大人になってから噛みにくさを感じるようになることもあります。軽度のズレでも長年放置すれば顎関節症やオーラルフレイルへつながるため、歯並びやかみ合わせの不調は早めの確認が大切です。
入れ歯・ブリッジ・被せ物の不具合
入れ歯やブリッジ、被せ物がうまく合っていないことも「噛めない」原因のひとつです。たとえば、入れ歯がぐらついてしっかり固定できない、金属の被せ物が高すぎて上下がうまく合わない、ブリッジの下に食べ物が入り込んで痛みが出るなど、補綴物の不適合によるストレスは意外と多く見受けられます。
特に部分入れ歯を長年使っている方は、「使えるから」と調整せずに放置している場合があり、知らず知らずのうちに噛み合わせがずれたり、他の健康な歯に負担がかかっているケースもあります。違和感を感じながら無理に使い続けると、さらなる歯の喪失や顎関節への悪影響を招く可能性があるため、定期的な調整や見直しが重要です。
和感を感じながら無理に使い続けると、さらなる歯の喪失や顎関節への悪影響を招く可能性があるため、定期的な調整や見直しが重要で
まずはつじむら歯科医院の症例をご覧ください!
まずはお口全体をチェックすることが第一歩
「噛めない」と一口にいっても、その背景には虫歯や歯周病、噛み合わせのズレ、補綴物の不具合など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。そのため、見た目だけでは原因が特定できないケースも多く、専門的な検査が必要になります。
咬合診査・レントゲン撮影・口腔内写真などを活用し、「なぜ噛みにくいのか」を丁寧に分析し、根本からの解決を目指す治療もあります。噛めないストレスから解放され、しっかり食事を楽しめる生活へ――。その第一歩として、ぜひ一度、お口の総合チェックにお越しください。
「噛みにくいかも…」と感じたら、今が受診のタイミングです。
噛む力の低下が体に及ぼす悪影響

「しっかり噛めない」状態を放っておくと、実はお口の問題だけにとどまりません。消化機能の低下や栄養不足、さらには認知機能や筋力の衰えにも関係してくることがわかっています。ここでは、噛む力の低下が全身に及ぼす影響を具体的に解説します。
消化機能や栄養吸収の低下
噛む力が弱くなると、食べものを細かく砕けず、消化器官に負担がかかります。十分に咀嚼されないまま食べものが胃へ届くことで、胃もたれや便秘、栄養の吸収効率の低下を引き起こすこともあります。
また、硬い食材を避けてしまうと、炭水化物中心の偏った食生活になりがちで、タンパク質やビタミンが不足し、体力や免疫力の低下にもつながります。
認知症やフレイルとの関連
噛むという行為は、脳を刺激し活性化させる効果があるといわれています。特に「海馬」や「前頭葉」といった記憶や判断力を司る部位が関係しており、しっかり噛む習慣がある人ほど、認知機能の維持が期待できます。
反対に、噛む回数が減ると脳への刺激も減少し、認知症リスクが高まる可能性があります。また、噛めないことで食事量が減り、筋力や体力も落ちやすく、フレイル(虚弱状態)へ進行する要因にもなります。
発音・表情筋への影響
噛む力の低下は、発音や表情にも関わってきます。噛む頻度が減ると口の周囲の筋肉が衰え、口角が下がったり、滑舌が悪くなったりします。
特に「サ行」や「タ行」が発音しづらくなることが多く、会話が不明瞭になると人とのコミュニケーションにも影響が出るかもしれません。さらに、唾液の分泌も減るため、口腔内の自浄作用が弱まり、虫歯や歯周病のリスクが高まることもあります。
噛めない=老化ではない?若い世代にも起こる理由

「噛めないのは年をとったから」と思われがちですが、実は若い世代でも噛みにくさに悩む方は少なくありません。親知らずや食生活の変化、ストレスによる食いしばりなど、現代人特有の要因も多くあります。ここでは、若年層に見られる噛みづらさの背景についてご紹介します。
親知らずや噛み合わせのズレ
20代前後に多いのが「親知らず」が原因となる噛み合わせの乱れです。親知らずが斜めや横に生えていると、隣接する歯を圧迫し、全体の歯並びに影響を及ぼすことがあります。また、上下の歯が正しく噛み合わなくなることで、片側だけに負担がかかり、噛みにくさや違和感につながることも。
歯並びのズレは本人が気づきにくいこともあるため、噛みにくい感覚がある場合は早めのチェックが大切です。
ストレスや食生活の影響
若い世代は、仕事や学業、人間関係などで日々ストレスを抱えやすく、無意識のうちに歯を食いしばったり、睡眠中に歯ぎしりをしたりする人が少なくありません。これらの習慣は、歯や顎関節に負担をかけ、痛みや疲れ、噛みにくさの原因になります。
特に朝起きたときに顎が重く感じたり、奥歯がすり減っているように感じたら、歯ぎしりや食いしばりの可能性があります。
また、柔らかい食べ物が好まれる現代の食習慣も一因です。噛む回数が減ることで咀嚼筋が衰え、噛む力そのものが弱まってしまいます。さらに、口をしっかり開けて食べる習慣が少ないと、あごの可動域が狭くなり、口を開けにくくなることもあります。
歯ぎしり・食いしばりの影響
歯ぎしりや食いしばりは、強い力で歯を噛みしめるクセのことで、自覚がないまま慢性的に続くと、歯がすり減ったり、知覚過敏になったりするだけでなく、噛むたびに痛みを感じたり、特定の歯が使いにくくなったりします。
症状が進行すると、顎関節に炎症が起き、開閉時に音がしたり、口が開きづらくなるケースもあります。
年齢に関係なく起こる「噛みにくさ」
このように、「噛めない」という悩みは年齢に関係なく起こりうる問題です。親知らずの影響、ストレスによる習慣、現代的な食生活などが複雑に絡み合い、若い世代でも日常の食事に支障をきたすことがあります。
違和感をそのままにせず、原因を見つけて対処することが、健康的な食生活と口元の機能を守るための第一歩です。
マウスピース矯正(インビザライン)で噛み合わせを整えるという選択肢

噛み合わせのズレが原因で噛みにくい場合、その改善方法として「マウスピース矯正(インビザライン)」という選択肢があります。見た目のためだけでなく、しっかり噛める機能を取り戻すための矯正として注目されています。ここでは、噛み合わせ治療としてのマウスピース矯正の魅力をお伝えします。
インビザラインは噛み合わせ調整にも対応
噛みにくさの原因として多いのが「噛み合わせのズレ」です。歯並びが乱れていたり、上下の歯が正しくかみ合っていないと、咀嚼に無意識のストレスがかかり、片側だけで噛んだり、顎が疲れたりといった症状が現れます。こうした噛み合わせの不調を改善する方法として、注目されているのがマウスピース矯正(インビザライン)です。
インビザラインというと「見た目を整える矯正」といった印象を持たれがちですが、実は噛み合わせの精密な調整にも適しています。独自の3Dシミュレーション技術を活用し、歯の動きを段階的に計算しながら、少しずつかみ合わせのバランスを整えていくことができます。
上下の歯がしっかりと接触するように配置が計画されるため、「奥歯で噛みしめられない」「前歯だけが当たる」といった偏りのある咬合も改善へ導くことが可能です。
金属を使わず、負担の少ない矯正
従来のワイヤー矯正に比べ、インビザラインは目立たず・痛みが少なく・取り外しができるのが特長です。食事のときには取り外せるため、硬い食材でもしっかり噛める機会を失わず、咀嚼力を落とさずに治療を続けられるという点も大きなメリットです。
また、金属による違和感や粘膜の傷つきが少ないため、口腔内に余計なストレスを与えず、顎関節や筋肉にも優しい設計といえます。痛みが少ないため、自然な咀嚼を保ちながら矯正できるのも、噛めない方にとっては安心できる要素です。
大人にも適した「快適な矯正」
インビザラインは、社会人や子育て中の方にも選ばれやすい理由があります。それは、治療中も生活スタイルを変えずに済むこと。仕事中も目立ちにくく、人前での会話や食事にも支障が出ません。
さらに、定期的な通院回数も比較的少なく、シミュレーション通りに進行するため、忙しい方でも続けやすい治療法です。「矯正=負担が大きい」というイメージが変わる、日常にフィットする噛み合わせ改善法といえるでしょう。
インビザライン矯正について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
機能回復としての矯正という考え方
噛めない理由が噛み合わせにあるなら、見た目のためだけでなく、機能の回復としての矯正治療を考える価値があります。特にマウスピース型のインビザラインは、機能性と快適性を両立した現代的な選択肢のひとつです。
義歯・入れ歯の不具合があるときの対処法

入れ歯やブリッジなどの補綴物は、失った歯の機能を補うために欠かせない存在です。しかし、長く使用しているうちに「外れやすい」「噛みにくい」といったトラブルを感じることもあります。ここでは、入れ歯の不具合の原因と、その対処法について詳しく解説します。
入れ歯が合わなくなる原因
入れ歯やブリッジなどの補綴物は、失った歯を補い、再び「噛む」機能を取り戻す大切な道具です。しかし、使い始めてしばらく経つと、違和感や不具合を感じることもあります。「噛みにくい」「痛い」「外れやすい」といった不調は、義歯の精度やお口の変化によって生じるもので、放置するとさらに噛みにくさが悪化することがあります。
入れ歯の不具合の原因のひとつに、顎の骨や歯ぐきの変化があります。特に総入れ歯を使用している場合、歯を支えていた骨が徐々に痩せていくことで、入れ歯がゆるくなったり、浮きやすくなったりします。また、部分入れ歯では、隣接する歯の傾きや、留め具(クラスプ)の変形によってフィット感が悪くなることもあります。
さらに、食いしばりや歯ぎしりなどの癖が入れ歯に過剰な力をかけてしまい、ゆがみや変形を招くケースも。これにより咀嚼バランスが崩れ、噛む力の左右差が生じることがあります。
調整・作り直しのタイミング
入れ歯を長く使っていると、日常生活の中で少しずつずれやすくなったり、痛みが出てきたりします。痛みを感じながら使い続けると、粘膜が傷ついて炎症を起こしたり、食べる意欲が低下したりする原因にもなります。
違和感を感じた場合は、無理せず調整を受けることが大切です。小さなズレであれば調整で改善できますが、長期間合わない入れ歯を使っていた場合は、作り直しが必要になることもあります。定期的な点検を受けることで、快適な状態を保ちやすくなります。
よく噛める入れ歯選びのポイント
よく噛める入れ歯を選ぶには、「自分の口にしっかり合っていること」が何よりも重要です。見た目や素材だけでなく、装着時の安定感、噛んだときの圧力の分散、発音のしやすさなど、総合的なバランスが求められます。
また、日常の使い方や食習慣、清掃の仕方によっても、入れ歯の持ちや快適さは大きく変わります。正しく手入れしながら、自分に合った入れ歯を使うことが、長く快適に過ごすための鍵となります。
食べにくさと「オーラルフレイル」の関係

最近「食べにくい」「噛みにくい」と感じる方は、オーラルフレイルという状態の入り口にいるかもしれません。加齢や生活習慣によって、口の機能が衰えていくこの現象は、全身の健康に密接に関わります。ここでは、オーラルフレイルとは何か、初期症状や予防のポイントについてご紹介します。
オーラルフレイルとは?
「最近、噛みにくくなった」「食べ物をこぼすことが増えた」――そんなささいな変化が、実はオーラルフレイルの始まりかもしれません。オーラルフレイルとは、加齢や口腔機能の衰えによって「食べる」「話す」「飲み込む」といった口の働きが徐々に低下していく状態のこと。進行すると、全身の健康にも影響を及ぼします。
フレイルとは、健康と要介護の中間にある虚弱な状態のことを指し、オーラルフレイルはその「口の機能」に限定したものです。しっかり噛めない、滑舌が悪くなる、むせやすいといった症状があらわれ始めると、口腔機能の低下が始まっている可能性があります。
最初は気づきにくい変化でも、食事量の減少や栄養不足、社会的な会話の減少につながり、体力や筋力の低下、さらには認知症や寝たきりのリスクへと発展することもあるため、見逃すことはできません。
初期症状に気づくために
オーラルフレイルの兆候は、日常の中に隠れています。たとえば、やわらかい物ばかり食べたがる、食べこぼしが増えた、以前より会話の声が小さくなった、なども一つのサインです。加えて、食後に口が疲れる、口臭が気になる、乾燥しやすいといった症状も見逃せません。
こうした変化にいち早く気づくことで、進行を食い止めることが可能になります。自分では気づきにくいため、家族や周囲の人が違和感に気づいたときも大切な判断材料になります。
放置しないためのセルフチェック
以下のような項目に当てはまるか、定期的に確認してみましょう。
・事に時間がかかるようになった
・食べこぼしやむせが増えた
・発音が不明瞭になってきた
・顎や口の周りが疲れやすい
2つ以上思い当たる場合は、オーラルフレイルの初期段階に入っている可能性があります。早めに対処することで、口の機能を維持し、健康的な生活を長く続けることができます。
かかりつけ歯科医院でできる噛み合わせ検査とは

噛みにくさや違和感を感じていても、原因がわからないまま過ごしている方も多いのではないでしょうか。そんなときは、歯科医院での噛み合わせ検査が大切な第一歩になります。ここでは、歯科医院で受けられる代表的な噛み合わせ検査と、その重要性についてご紹介します。
咬合力測定・顎の動きの確認
「噛みにくい」「噛むと違和感がある」「どの歯で噛んでいるか分からない」――こうした症状は、噛み合わせに問題があるサインかもしれません。噛み合わせのズレは、見た目ではわかりづらく、放置すると全身のバランスにも影響を及ぼすことがあります。そこで重要になるのが、歯科医院で行う噛み合わせ検査です。
噛み合わせの検査では、まず咬合力(噛む力)を専用の機器で測定します。どの歯に力が集中しているか、左右のバランスはどうかなどを数値で把握することができます。力のかかり方に偏りがあると、歯のすり減りや顎の疲労、頭痛の原因になることも。
また、顎の開閉時の動きや音、ズレがないかを視診や触診で確認します。顎関節症の初期症状は自覚しにくいため、こうしたチェックによって早期発見につながります。
定期検診での早期発見の重要性
噛み合わせの異常は、急に悪くなるというよりも、少しずつ進行していくのが特徴です。最初は食べづらさや軽い顎のだるさ程度でも、放置すれば次第に慢性的な痛みや歯の欠損、顎関節のトラブルへと発展することがあります。
そのため、定期的な歯科検診で噛み合わせの状態を把握しておくことがとても重要です。虫歯や歯周病だけでなく、噛み合わせや咀嚼機能も含めたチェックを行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
専門的な検査機器を活用した診断
近年では、コンピューターを用いた咬合診断システムや、顎の動きをリアルタイムで記録できる機器も登場しています。これらを使うことで、従来の視診だけでは見つけにくかった微細なズレも明らかになります。
検査結果はグラフや画像で可視化されるため、自分の口の状態を理解しやすく、適切な治療方針を立てるうえでも有効です。数値や動きの記録をもとに、必要であれば矯正や補綴などの治療を提案することもあります。
よく噛めるようになるためのトレーニングと工夫

噛む力は、鍛えることによって改善できる場合があります。食事や姿勢、咀嚼筋のトレーニングなど、日常のちょっとした工夫が、噛みやすさにつながります。ここでは、簡単にできる「噛む力アップ」のためのトレーニングや生活習慣のポイントをご紹介します。
噛む筋力を鍛えるトレーニング
「噛みにくさ」を感じても、すぐに治療が必要とは限りません。噛む力の低下は、日常生活のちょっとした意識やトレーニングで改善できる場合もあります。噛む筋肉や顎の動きは、使わなければ衰えていく一方ですが、逆に少しずつ鍛えることで、機能を取り戻すことも可能です。
咀嚼に使われる筋肉(咬筋や側頭筋)は、加齢だけでなく、噛む回数の減少によっても弱くなります。毎日の食事の中で、意識して「よく噛む」ことが最も基本的なトレーニングです。目安としては、一口あたり30回を意識すると効果的です。
また、ガムを左右均等に噛む、舌を上あごにつけて押し上げる「舌筋トレーニング」なども口まわりの筋力強化に役立ちます。無理なく継続できる簡単な運動から始めるのがおすすめです。
噛みやすい食材・調理の工夫
いきなり硬いものを食べようとすると、かえって顎や歯に負担がかかる場合があります。最初はやわらかいけれど咀嚼回数が増えるような食品、たとえば蒸した根菜類や繊維のある果物などを取り入れるのが効果的です。
さらに、食材を大きめに切って噛む回数を増やす、弾力のある食材(こんにゃくやきのこなど)を意識的に取り入れるなど、調理の工夫次第で自然と噛む習慣を促すことができます。
食事姿勢・左右バランスを意識する
正しい姿勢で食事をすることも、よく噛むための重要なポイントです。猫背になっていたり、顎を突き出すような姿勢では、咀嚼筋にうまく力が入らず、片側だけで噛むクセがついてしまう原因になります。
また、片方の歯ばかり使っていると、歯や顎に左右差が出てしまい、噛み合わせの不調や痛みにつながることもあります。日頃から「今日は右側でも噛んでみよう」と意識するだけでも、咀嚼のバランスを整える効果があります。
マウスピース矯正で噛めるを取り戻すという選択肢

噛みにくさの根本的な原因が歯並びや噛み合わせのズレにある場合、矯正治療は有効な手段となります。特にマウスピース矯正(インビザライン)は、快適さと機能性を兼ね備えた治療法として、多くの方に選ばれています。ここでは、噛める口を取り戻すための矯正という考え方について掘り下げます。
噛み合わせのバランスを整える矯正治療
「しっかり噛めない」「噛み合わせが合わない」そんな違和感は、日々の食事や会話に小さなストレスを生み出します。こうした悩みに対して、見た目だけでなく噛む機能まで改善できる方法として注目されているのが、マウスピース矯正(インビザライン)です。
噛み合わせが乱れていると、左右で噛む力に差が出たり、一部の歯にだけ負担が集中することで、あごの疲れや噛みにくさが起こります。マウスピース矯正では、歯を少しずつコントロールしながら全体のかみ合わせを正しい位置へ誘導していきます。
精密な3Dシミュレーションにより、上下の歯がきちんと接触するように設計されており、「奥歯でしっかり噛めない」「前歯しか当たらない」といった咬合のズレにも対応可能です。
食事を我慢しない矯正だから、咀嚼力を保てる
マウスピース矯正の大きなメリットのひとつが、取り外し可能であることです。食事のたびに外せるため、矯正中でも食べものをしっかり噛むことができ、咀嚼筋を保ちながら治療を続けることができます。
さらに、金属のワイヤーやブラケットがないため、口内炎や粘膜の傷を避けられ、治療中の違和感も最小限に抑えられます。「矯正で噛みにくくなったらどうしよう」と不安な方にも、安心して始められる治療法といえます。
治療のゴールが噛める未来であるために
マウスピース矯正は、ただ見た目を整えるだけではありません。治療開始前には治療後のかみ合わせを3D画像で確認でき、どのように「噛めるようになるか」が事前にイメージできます。
また、インビザラインは成人矯正にも広く対応しており、仕事や家事、子育てと両立しながら無理なく続けることができるため、「今さら矯正なんて」と迷っていた方にもぴったりです。
まずは、噛み合わせの状態を知ることから
「マウスピース矯正で本当に噛めるようになるの?」そう感じている方も多いと思います。噛みにくさの原因は、人によって異なり、歯列やあごの動き、日常の癖までさまざまです。
咬合診査や精密検査に基づき、噛み合わせ改善を目的とした矯正治療もあります。マウスピース矯正がご自身に合うかどうかは、まず「今のかみ合わせ」を知ることから。
「噛みにくさをなくしたい」「将来もしっかり食べられる口でいたい」と感じたら、小さな違和感のうちに、お気軽にご相談ください。
気になる症状がある方は、お早めに専門医へ。
神奈川県伊勢原市の
見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)
『 つじむら歯科医院 伊勢原 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士