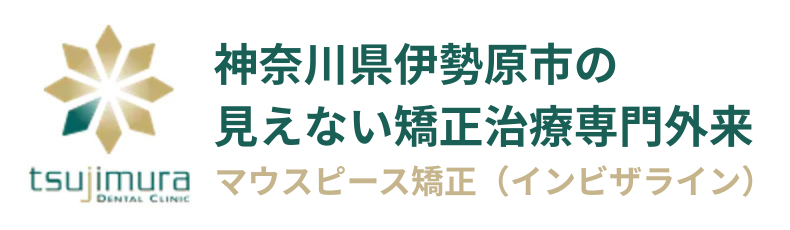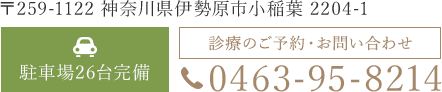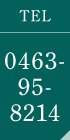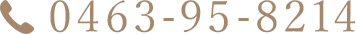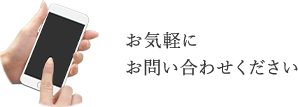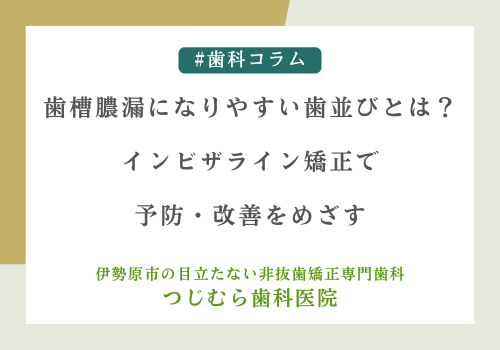
歯槽膿漏とは?放っておくとどうなるのか

「歯ぐきが腫れている」「歯ブラシに血がつく」「なんだか口臭が気になる」――そんな症状があっても、「たいしたことはない」とそのままにしていませんか?これらは、歯槽膿漏(しそうのうろう)の初期サインかもしれません。歯槽膿漏は、歯周病の進行した状態であり、放置すると歯が抜けてしまう危険性もある深刻な疾患です。まずは、歯槽膿漏とは何か、そして進行するとどうなるのかを正しく知ることから始めましょう。
歯周病の進行状態(歯槽膿漏)とは?
歯槽膿漏とは、歯周病の中でも重度に進行した状態を指します。歯周病は、歯ぐきと歯の間にある歯周ポケットにプラーク(歯垢)が溜まり、そこに潜む細菌が炎症を引き起こすことから始まります。初期には「歯肉炎」と呼ばれる段階で、歯ぐきの腫れや出血などの症状がみられますが、さらに進行すると歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、歯がグラついたり、最終的には自然に抜け落ちてしまうこともあります。これが「歯槽膿漏」の状態です。
自覚症状の少なさと進行の怖さ
歯槽膿漏の最も厄介な点は、自覚症状が出にくいまま進行することです。虫歯のような鋭い痛みがほとんどないため、本人が異変に気づかず、気づいたときにはすでに手遅れ…というケースも珍しくありません。「ちょっと歯ぐきが腫れているかな?」と思っている間にも、目に見えないところで歯周組織の破壊が進行しています。また、痛みがないことで歯科受診が遅れ、結果的に抜歯が必要になるほど重症化するリスクも高くなります。
歯のグラつき・口臭・抜けるリスク
歯槽膿漏が進行すると、歯ぐきが下がって歯の根が露出し、冷たいものがしみる・歯がグラグラするといった症状が現れます。また、歯周ポケットに膿が溜まることで、強い口臭が発生することも。さらに、歯を支える骨が溶けてしまうため、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。こうなると、食事が困難になるだけでなく、見た目や発音にも影響し、日常生活の質を大きく損ないます。歯槽膿漏は「自然に治るものではない」ため、早期の発見と専門的な治療が不可欠です。
不安を感じている方へ、実際の治療例をご紹介しています。
歯並びと歯槽膿漏の意外な関係

歯槽膿漏といえば「歯みがき不足」や「加齢」が原因と思われがちですが、実は歯並びも密接に関係しています。歯列の乱れは見た目の問題にとどまらず、日々の清掃性や噛み合わせのバランスにも影響し、知らぬ間に歯周病のリスクを高める要因となるのです。この章では、歯並びが歯槽膿漏を招く理由を「磨き残し」「プラークの蓄積」「噛み合わせによる負担」の3つの視点からわかりやすく解説します。
歯列の乱れ=磨き残しの原因
歯がガタガタに並んでいる、あるいは一部が重なっているといった歯列の乱れは、日常の歯みがきを難しくします。歯ブラシの毛先が届きにくい部分には、自然と磨き残しが生じやすくなります。特に、叢生(ガタガタの歯並び)や奥歯の入り組んだ箇所は、目で見えないうえに感覚的にも磨けているか分かりづらいため、清掃が不十分になりやすいのです。その結果、歯垢(プラーク)が蓄積し、歯ぐきに炎症が起こりやすくなります。毎日しっかり磨いているつもりでも、歯並びの乱れがあるだけで歯槽膿漏へのリスクが高まってしまうのです。
プラークの蓄積が炎症につながる仕組み
プラークとは、細菌のかたまりであり、歯と歯ぐきの境目に付着すると炎症を引き起こします。通常は歯みがきで取り除くことができますが、歯並びが悪く磨き残しが多い箇所では、プラークがそのまま放置され、やがて歯石となって硬く固着します。歯石は歯みがきでは取れず、さらにその表面にプラークが付着しやすくなるため、悪循環に陥ります。炎症が慢性化すると歯周ポケットが深くなり、歯槽骨が溶けていく――これが、歯槽膿漏に至るメカニズムです。つまり、歯並びの悪さは、「プラークが溜まりやすい環境」をつくってしまう要因なのです。
噛み合わせが悪いことで負荷が集中し、歯ぐきが傷むケースも
歯並びが乱れていると、噛み合わせにもズレが生じやすくなります。正しく咬合されていない場合、特定の歯や歯ぐきに咬む力が集中してしまい、そこに慢性的なダメージが加わります。このような状態は「咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)」と呼ばれ、歯周組織にストレスを与えて炎症を助長する原因となります。特に、前歯だけで噛む「開咬」や上下の歯が噛み合わない「交叉咬合」の場合、歯ぐきへの負荷が不均一になりやすく注意が必要です。噛み合わせの乱れもまた、歯槽膿漏の見落とされやすい引き金といえるでしょう。
歯槽膿漏になりやすい歯並びの特徴

歯並びの乱れは、見た目や発音の問題として注目されがちですが、実は「歯周病になりやすいかどうか」にも大きな影響を与えます。歯と歯の間に汚れがたまりやすかったり、噛み合わせのバランスが崩れたりすることで、歯ぐきへの負担が増し、結果として歯槽膿漏のリスクを高めてしまうのです。この章では、特に歯槽膿漏になりやすいとされる歯並びのタイプを4つご紹介し、それぞれの注意点について解説します。
叢生(ガタガタの歯並び)
叢生(そうせい)とは、歯が前後に重なり合い、ガタガタに並んでいる状態のことを指します。歯がきれいに並ぶスペースが足りないことが主な原因で、見た目の印象だけでなく、清掃性にも大きな問題があります。歯ブラシの毛先が届きにくく、磨き残しが発生しやすいため、プラークが蓄積して歯ぐきに炎症が起こりやすくなります。叢生があると、毎日きちんと歯みがきをしていても、清掃が行き届かないことが多く、歯槽膿漏のリスクが非常に高まる歯並びのひとつです。
開咬(奥歯しか噛まない状態)
開咬(かいこう)とは、前歯がしっかり噛み合わず、奥歯だけで咬合している状態を指します。このような噛み合わせでは、食べ物を前歯で噛み切るのが難しくなるだけでなく、噛む力が特定の歯に集中することで、歯ぐきや歯周組織への負担が偏ってしまいます。また、前歯の隙間に食べかすが溜まりやすく、清掃しにくいという面でも歯周病のリスクが高まります。開咬は見た目以上に、口腔内の健康に悪影響を与える歯並びの一つです。
交叉咬合(すれ違った噛み合わせ)
交叉咬合(こうさこうごう)は、上下の歯が部分的にすれ違ってしまい、左右のバランスが崩れている状態を指します。このような噛み合わせでは、正常な咀嚼が難しくなるだけでなく、一部の歯に力が集中することで、歯ぐきにストレスがかかりやすくなります。また、ずれた歯同士の接触によって歯や歯ぐきを傷つけやすく、炎症や歯槽骨の破壊が起こる可能性もあります。交叉咬合は、見落とされがちな歯槽膿漏リスクのひとつです。
出っ歯・受け口も清掃不良の原因に
出っ歯(上顎前突)や受け口(下顎前突)も、清掃性の低下を招く歯並びです。前歯が前方に大きく出ていると、唇でカバーしづらく乾燥しやすくなり、細菌が繁殖しやすくなります。また、歯ブラシが届きにくい部分も多く、結果として磨き残しが多くなりがちです。見た目のコンプレックスだけでなく、歯周病のリスク要因であることを知り、早めに対処することが大切です。
出っ歯(上顎前突)について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
受け口(下顎前突)について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
どんな人が歯槽膿漏になりやすいのか

歯槽膿漏の発症には、歯並びの乱れだけでなく、生活習慣や全身の健康状態など、さまざまな要因が影響しています。つまり、同じような歯並びでも、日々のケアや体質によって進行のスピードは異なるということです。この章では、「歯並び以外にどんなリスク要因があるのか」「どんな生活習慣が歯槽膿漏を招きやすいのか」を中心に、歯周病になりやすい人の特徴をわかりやすく解説します。
歯並び以外のリスク要因:喫煙・ストレス・口呼吸・糖尿病など
歯槽膿漏の進行には、口腔内の環境だけでなく、全身的な要因も深く関係しています。代表的なリスクのひとつが喫煙です。たばこに含まれる有害物質は歯ぐきの血流を悪化させ、免疫機能を低下させるため、炎症が進行しやすくなります。さらに、喫煙者は歯ぐきの出血が抑えられる傾向があるため、歯周病の進行に気づきにくく、重症化しやすいのが特徴です。
また、ストレスも免疫力の低下や唾液量の減少につながり、細菌が繁殖しやすくなります。現代人に多い「口呼吸」も、口の中を乾燥させてプラークの蓄積を促す要因となり、特に睡眠中に口を開けている人は要注意です。
さらに、糖尿病との関連も見逃せません。血糖値が高い状態では、炎症が起きやすく傷の治りも遅いため、歯周病が悪化しやすくなります。実際、糖尿病と歯周病は相互に悪影響を及ぼす関係として知られており、歯槽膿漏の予防には内科的な管理も重要です。
このように、生活習慣や全身の疾患もまた、歯ぐきの健康に大きな影響を与えることを知っておきましょう。
年齢・生活習慣・セルフケアの影響
歯槽膿漏は年齢とともにリスクが高まる傾向があり、特に40代以降では顕著に増加します。年齢を重ねることで歯ぐきの再生能力が低下し、細菌への抵抗力も弱まるため、若い頃と同じようなケアでは十分に予防できないケースも出てきます。また、生活の忙しさから歯科受診を後回しにする人も増え、知らないうちに進行していることも少なくありません。
さらに、セルフケアの質も歯槽膿漏の発症に大きく関係します。正しい歯みがきができていない、歯間ブラシやデンタルフロスを使っていない、寝る前に歯を磨かない習慣がある――こうした日常の小さなおろそかが積み重なり、プラークの蓄積を招きます。また、「歯医者は痛くなってから行くもの」という意識が強い人ほど、歯周病の早期発見が難しく、重症化しやすくなります。
つまり、歯槽膿漏は「特別な人だけがかかる病気」ではありません。誰にでもリスクはあり、生活習慣やセルフケアの積み重ねで、そのリスクは大きく変わるのです。特に最近、歯ぐきの状態に違和感を覚えている方は、ぜひ一度、歯科医院でのチェックをおすすめします。
今すぐチェック!歯の健康を守るためにWEB予約を
インビザライン矯正とは?目立ちづらく快適な新しい選択肢

歯並びを整える治療と聞くと、ワイヤー矯正を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし近年では、見た目の自然さや快適さから「マウスピース矯正」を選ぶ方が増えています。中でも注目されているのが「インビザライン矯正」です。透明なマウスピースで目立ちにくく、取り外しもできるため、歯ぐきや歯周病のケアもしやすい点が大きな魅力。ここでは、インビザラインの特徴やメリットについて、従来の矯正と比較しながらご紹介します。
ワイヤーと比較した特徴
従来の矯正治療では、金属製のワイヤーとブラケットを歯に装着して歯を動かしていきます。この方法は矯正力に優れている一方で、「目立つ」「痛みや違和感がある」「食事や歯みがきがしにくい」などの課題もありました。インビザラインは、これらのデメリットを大きく軽減した治療法です。透明なマウスピースを使うため装着していても目立たず、見た目を気にすることなく矯正が進められます。
また、金属を使わないので金属アレルギーの心配もありません。仕事やプライベートで人前に出る機会が多い方にとって、負担の少ない選択肢といえるでしょう。
取り外し可能だから清潔に保ちやすい
インビザラインの大きな特徴の一つは「自分で取り外せる」ことです。食事の際にはマウスピースを外せるため、従来のワイヤー矯正のように食べ物が詰まる心配がなく、好きなものを楽しむことができます。また、歯みがきやフロスも普段通りに行えるため、口腔内を清潔に保ちやすく、むし歯や歯周病の予防にもつながります。特に歯ぐきの健康が気になる方にとって、「取り外してしっかりケアできる」というのは非常に大きなメリットです。衛生面を重視する方にとって、インビザラインは非常に合理的な治療法といえるでしょう。
インビザラインのメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
インビザライン矯正について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
治療中の口腔ケアがしやすい利点
ワイヤー矯正中は、装置の周囲に食べかすや歯垢がたまりやすく、日々の口腔ケアが難しくなりがちです。これに対してインビザラインでは、マウスピースを外していつも通りに歯みがきができるため、治療中でも口腔内を清潔に保ちやすいという利点があります。これは、歯槽膿漏を予防するうえで非常に重要なポイントです。矯正治療中は歯ぐきにも負担がかかりやすいため、しっかりとしたケアが欠かせません。インビザラインなら、歯並びの改善と同時に歯ぐきの健康も守りやすい環境が整っていると言えるでしょう。
インビザラインで歯槽膿漏リスクを減らせる理由

歯槽膿漏の予防には、毎日の丁寧な歯みがきや生活習慣の見直しが欠かせません。しかし、実は「歯並びを整えること」も大きな予防効果をもつことをご存じでしょうか?特にインビザライン矯正は、見た目の改善だけでなく、清掃性や噛み合わせのバランスを整えることで、歯ぐきの健康維持にも貢献します。この章では、インビザラインが歯槽膿漏のリスク軽減にどのように役立つのか、3つの観点からご紹介します。
歯並びを整えることで清掃しやすくなる
歯並びが乱れていると、歯と歯の間に歯ブラシが届きにくく、プラークがたまりやすくなります。その結果、歯ぐきに炎症が起こりやすくなり、歯槽膿漏のリスクが高まります。インビザラインで歯列を整えることで、歯みがきがしやすくなり、毎日のセルフケアの精度が大きく向上します。特に、叢生(ガタガタの歯並び)やすきっ歯などの方は、矯正後に「歯みがきがラクになった」「フロスが通しやすくなった」と実感されることが多く、結果として歯周病のリスクを軽減しやすくなるのです。
正しい噛み合わせで歯ぐきへの負担も軽減
噛み合わせが悪いと、特定の歯や歯ぐきに咬合力が集中し、長期的には歯周組織にダメージを与える「咬合性外傷」が起こることがあります。こうした負担が蓄積すると、炎症が慢性化しやすくなり、歯槽膿漏のリスクを高める要因となります。インビザラインは、ただ見た目を整えるだけでなく、機能的な咬合バランスを目指した矯正が可能です。正しい噛み合わせを獲得することで、歯ぐきにかかる不均等なストレスを軽減し、歯周病の進行を防ぐ環境をつくることができます。
矯正中も衛生管理しやすいから安心
従来のワイヤー矯正では、装置の周りに食べかすや歯垢がたまりやすく、治療中の口腔ケアに苦労する方が少なくありません。インビザラインは取り外しが可能なため、治療中でも普段通りに歯みがきやフロスができるのが大きな魅力です。これは、歯ぐきの健康を保つうえで非常に重要なポイントです。特に歯周病予備軍の方や歯ぐきの状態に不安がある方にとって、「矯正中も口腔内を清潔に保てる」ことは大きな安心材料となります。インビザラインは、見た目の変化だけでなく、健康維持にもつながる矯正治療といえるでしょう。
歯周病が進んでいても矯正はできる?

「歯並びを治したいけれど、歯周病もあるし矯正できるのかな…?」そんな不安を抱えている方は少なくありません。実際に、歯周病が進行している場合には、そのまま矯正治療を始めることはおすすめできません。しかし、治療をあきらめる必要はありません。歯ぐきの状態をきちんと整えたうえで適切な処置をすれば、インビザライン矯正が可能になるケースも多くあります。この章では、歯周病と矯正治療の関係について、注意点やポイントを解説します。
歯周病治療を優先する必要があるケース
歯周病が進行している状態でそのまま矯正治療を始めると、歯を支える骨や歯ぐきが弱っているため、矯正の力によって状態がさらに悪化するリスクがあります。そのため、歯周病がある場合は、まずは歯周治療を優先することが大前提です。
具体的には、プラークや歯石の除去、歯ぐきの炎症を抑える処置、必要に応じて外科的な治療などを行い、歯周組織の安定を図ります。歯ぐきの腫れや出血が落ち着き、歯周ポケットが改善された状態になって初めて、安全に矯正治療に移行できるのです。
歯ぐきの状態が安定すれば矯正も可能
「歯周病があるから矯正はできない」と思い込んでしまう方も多いですが、実際には歯ぐきの状態が安定していれば、インビザラインなどの矯正治療を行うことは可能です。むしろ、歯並びを整えることで清掃性が向上し、歯周病の再発予防にもつながるケースが少なくありません。
インビザラインは取り外しができるため、矯正中もセルフケアを続けやすく、歯ぐきに配慮した治療が行いやすい点も利点です。大切なのは、現状をきちんと診断し、治療の順番とタイミングを見極めること。まずは歯科医院での精密な診査を受けることが第一歩となります。
歯並びと歯ぐき、両方を守るには

歯並びの改善は、見た目を美しく整えるだけでなく、歯ぐきや歯の寿命を守ることにもつながります。近年では、歯周病ケアと矯正治療の両立が重視されるようになり、長期的にお口の健康を維持するための総合的な治療が求められています。この章では、「歯周病ケア×矯正」という視点から、歯並びと歯ぐきの両方を守る方法と、見た目だけでなく機能と健康を意識した治療方針について解説します。
歯周病ケア×矯正=長期的な口腔健康の維持
歯周病と矯正治療は、別々のものと考えられがちですが、実は相互に深く関係しています。歯周病は進行すると歯を支える骨や歯ぐきを破壊してしまい、歯並びにも影響を与えます。一方で、歯並びが乱れていると歯みがきがしづらくなり、歯周病の進行を促してしまうことも。つまり、歯周病と歯列不正は、互いに悪影響を及ぼし合う関係にあるのです。
このため、歯周病がある場合はまず炎症を抑えたうえで、歯並びの改善を行うことが大切です。矯正によって歯列を整えることで清掃性が向上し、再発のリスクを抑えられるというメリットもあります。さらに、矯正中も定期的な歯周メンテナンスを行うことで、健康な歯ぐきを維持しやすくなります。見た目の美しさだけでなく、長期的な口腔の健康を支える治療として、歯周病ケアと矯正を組み合わせたアプローチが注目されています。
「見た目」だけでなく「歯の寿命」まで考えた治療方針
歯並びの矯正というと、「見た目をきれいにする」ことが目的だと思われがちですが、それだけではありません。正しい噛み合わせや清掃性の向上によって、歯や歯ぐきにかかる負担を軽減し、結果として歯の寿命を延ばすことにもつながります。特に、将来的に歯を1本でも多く残すことは、健康寿命の延伸や生活の質(QOL)の維持にも直結します。
矯正治療を検討する際は、「見た目を良くしたい」だけでなく、「歯ぐきを健康に保ちたい」「歯を長持ちさせたい」といった目的を持つことで、治療の意義がより深まります。インビザライン矯正は、審美性と清掃性のバランスが取れた治療法であり、歯ぐきにもやさしい選択肢です。将来の自分のために、今できる口腔ケアを始めていくという視点が、これからの歯科医療には欠かせません。
よくある質問Q&A(インビザラインと歯周病編)

インビザライン矯正に興味はあっても、「歯ぐきが弱いけど大丈夫?」「ケアが難しそう…」といった不安から一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか。特に、歯周病や歯槽膿漏に悩んでいる方にとっては、矯正治療へのハードルが高く感じられることも少なくありません。この章では、歯周病とインビザラインに関して寄せられるよくある質問を3つ取り上げ、安心して治療を始めていただくための情報をわかりやすくご紹介します。
歯ぐきが弱い人でもインビザライン矯正はできますか?
はい、歯ぐきの状態によってはインビザライン矯正が可能です。ただし、歯周病が進行している場合には、まず歯周治療を優先することが大切です。炎症があるまま矯正を始めてしまうと、歯を支える骨や歯ぐきにさらなるダメージを与える可能性があるため、状態が安定してから治療を開始します。
インビザライン中の歯みがきは難しくないですか?
いいえ、むしろインビザラインは取り外しができるため、矯正中でも普段通りの歯みがきが可能です。ワイヤー矯正では装置の周りに歯垢が溜まりやすく、細かいケアが必要ですが、インビザラインはマウスピースを外してから歯を磨けるので、衛生管理がしやすいのが大きな特徴です。
また、フロスや歯間ブラシも使いやすいため、歯ぐきへの負担を抑えながら日常的なケアを続けることができます。矯正中でもしっかりと歯周病予防をしたい方には、特におすすめの治療法です。
治療中に痛みはありますか?
インビザラインは、比較的痛みの少ない矯正方法とされています。新しいマウスピースに交換した直後は、歯が動くことによる軽い圧迫感や違和感を感じることがありますが、通常は数日で慣れる方がほとんどです。金属ワイヤーのように頬や舌に当たって傷ができる心配もなく、装着中のストレスが少ないのも魅力の一つです。痛みに敏感な方や、過去にワイヤー矯正で辛い思いをされた方でも、快適に続けやすい矯正治療として人気があります。不安な点は事前にご相談いただければ、対応方法やケアのアドバイスも丁寧にお伝えしますのでご安心ください。
歯ぐきの不安を感じたら、まずは相談から

将来のために、今できる一歩を
歯槽膿漏や歯周病は、静かに進行するため放置しやすく、気づいたときには歯ぐきや骨に大きなダメージが出ていることも珍しくありません。とはいえ、早い段階で正しく対応すれば、進行を止めたり、将来的なトラブルを予防することが可能です。歯ぐきの異変を「年齢のせい」や「たいしたことない」と見過ごさず、小さな違和感のうちに歯科医院へ相談することがとても大切です。
矯正治療に関しても、「自分には関係ない」と思い込まず、口腔環境を整える手段の一つとして前向きに捉えてみてください。歯並びや噛み合わせが整うことで、セルフケアのしやすさが格段に変わり、結果として歯周病のリスクを大きく下げることにつながります。
どんなお悩みも、まずはご自身の状態を知るところから始まります。「もっと早く相談すればよかった」とならないよう、気になることがあればぜひ歯科医院へ足を運んでみてください。健康な歯と歯ぐきを守るために、今できることを一緒に考えていきましょう。
お口のお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
神奈川県伊勢原市の
見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)
『 つじむら歯科医院 伊勢原 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士