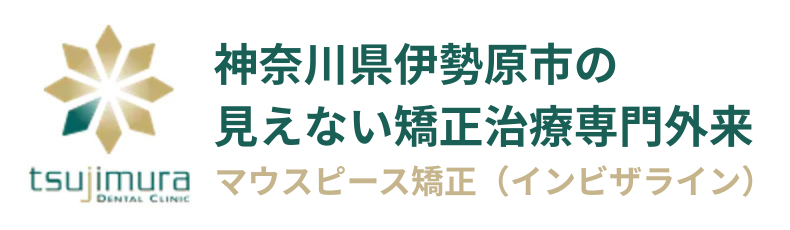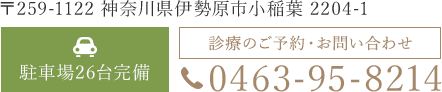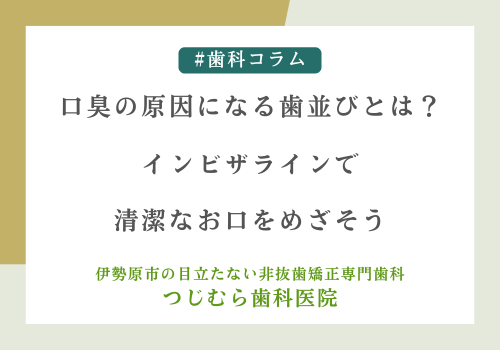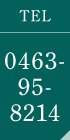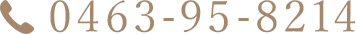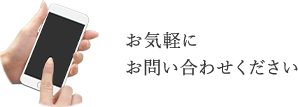口臭の悩み、実は歯並びが関係している?

「毎日しっかり歯を磨いているのに、なんとなく口臭が気になる…」そんな悩みを抱える方は少なくありません。実は、その原因のひとつとして見落とされがちなのが「歯並び」です。ここでは、歯並びと口臭の意外な関係に迫ります。
毎日歯磨きしているのに口臭が消えない理由
口臭が気になるとき、多くの人は「歯磨きが足りないのかな」と考えます。しかし、丁寧にブラッシングをしても改善されない場合、その裏には歯並びが関係していることがあります。歯並びが乱れていると、歯ブラシの毛先が届きにくい部分が増え、結果的に「磨き残し」が発生しやすくなるのです。特に奥歯の後ろや歯と歯の重なり部分はプラークが溜まりやすく、口臭の原因物質を生む細菌が繁殖する温床になります。
つまり、清掃の努力だけでは解決できない「物理的な届きにくさ」が、根本的な口臭の原因になっているケースがあるのです。このことを理解していないと、どれだけケアを続けても「なんだかスッキリしない」という状態から抜け出せません。
一般的な「口臭の原因」と歯並びの意外な関係
口臭の原因としては、舌苔(ぜったい)や食べかす、歯周病、虫歯、さらには胃腸の不調など、さまざまな要因が挙げられます。しかし近年、歯並びの乱れがこれらの原因と密接に関係していることが分かってきました。特に叢生(そうせい)と呼ばれるガタガタの歯並びは、細菌が溜まりやすくなるだけでなく、食べかすが長時間残る原因にもなります。
また、口呼吸の癖がある方は歯列に影響が出やすく、常に口内が乾燥してしまうことで細菌が増殖しやすくなり、結果として不快なニオイが発生します。つまり、口臭対策を考える上で「歯並びの状態を見直す」という視点が重要なのです。
歯並びが口臭を悪化させるメカニズムとは
歯並びが悪いと清掃性が低下し、歯垢が溜まりやすくなります。歯垢は細菌の集合体であり、そこから発生する「揮発性硫黄化合物(VSC)」というガスが、強い口臭の原因になります。特に、歯と歯が重なっている箇所や、歯列の外側・内側でブラシが入りづらい場所は、菌の温床となります。
さらに、歯並びが悪いことで噛み合わせも崩れやすくなり、しっかりと噛むことができないと唾液の分泌量が減少します。唾液には口内を清潔に保つ作用がありますが、その量が足りないと自浄作用が働かず、ますますニオイの元が溜まってしまうのです。
こうした悪循環を断ち切るには、単に口臭ケアをするだけでなく、「磨ける歯並び」へと整えることが根本的な解決策になります。
口臭の原因になりやすい歯並びのタイプ

歯並びの乱れがあると、それだけで口臭のリスクが高まります。とくに口臭の原因になりやすい特定の歯列タイプには注意が必要です。ここでは、日常的に見られる歯並びのタイプ別に、どのように口臭と関係しているのかを詳しくご紹介します。
叢生(ガタガタの歯並び)はプラークの温床
叢生とは、歯が重なり合って並んでいる状態のことで、「ガタガタの歯並び」とも言われます。日本人に比較的多い歯列不正のひとつで、見た目の問題だけでなく、清掃性の悪さが大きなデメリットです。歯ブラシの毛先が届きにくい場所が多いため、歯垢や食べかすが残りやすく、結果として細菌の繁殖を招きます。
特に、前歯の重なりや奥歯の内側などは、丁寧に磨いたつもりでも磨き残しが多くなりやすい部分。こうした部分では、口臭の原因となる揮発性硫黄化合物(VSC)を発生させる細菌が活動しやすく、慢性的なニオイの悩みにつながるのです。
開咬(前歯が噛み合わない)で唾液が減少
開咬とは、奥歯は噛んでいるのに前歯同士が噛み合わず、上下にすき間ができている歯並びです。このタイプの歯並びでは、前歯で食べ物をしっかり噛み切ることができず、咀嚼が不十分になりがちです。その結果、唾液の分泌が促進されにくく、口腔内が乾燥しやすくなります。
唾液には、口の中を洗い流し、細菌の繁殖を防ぐ「自浄作用」があります。しかし、開咬のように噛む力が分散してしまうと、この唾液の分泌量が減少し、口臭のリスクが高まるのです。また、口が常に少し開いた状態になりやすいため、無意識のうちに口呼吸になる方も多く、これも乾燥を悪化させる一因となります。
交叉咬合・過蓋咬合による噛み合わせの偏り
交叉咬合は、上下の歯が部分的にすれ違って噛み合う状態を指し、過蓋咬合は、上の歯が下の歯を深く覆いすぎる噛み合わせのことです。これらの歯並びでは、噛む力が一部の歯に偏りやすく、歯ぐきや歯に過剰な負担がかかることがあります。
その影響で歯肉炎や歯周病が起きやすくなり、歯周病由来の口臭を引き起こす原因となります。また、咀嚼時のバランスが悪いために食べかすが歯の片側に溜まりやすく、片側だけ汚れが目立つ「左右差」がある方も少なくありません。日常の歯磨きでは気づきにくいこの差が、口臭の一因となっていることもあります。
歯ブラシが届かない場所がにおいの温床に

毎日歯磨きをしていても、実際には口の中すべてを完璧に磨けている人は少ないのが現実です。特に歯並びが乱れていると、どうしてもブラシが届かない死角が生まれます。そこが、口臭の原因となる細菌の繁殖場所になっているのです。
磨き残しが細菌繁殖を引き起こす
歯ブラシは直線的に動かす道具です。そのため、歯が重なり合ったり、ねじれていたりする部位には毛先が届きにくく、どうしても磨き残しが発生します。特に叢生のある方や八重歯、奥歯が斜めに生えている方は、日々のブラッシングでは十分に清掃できていないことが多いのです。
こうした磨き残しの箇所には、食べかすや歯垢が蓄積し、細菌が繁殖していきます。これらの細菌が活動する際に発生するガスが「揮発性硫黄化合物(VSC)」と呼ばれるもので、まさにあの独特な「口臭」の元になる物質です。つまり、どれだけ丁寧に磨いたつもりでも、届いていない場所がある限り、口臭は発生し続けてしまうのです。
歯垢・歯石が揮発性硫黄化合物(VSC)を発生
口臭の原因物質であるVSCは、歯垢(プラーク)や歯石に棲みついた嫌気性細菌によって作り出されます。これらの細菌は酸素の少ない環境を好み、歯と歯の間や歯ぐきの奥など、空気が届きにくいところに潜んでいます。
このような場所は通常のブラッシングだけでは除去が難しく、時間が経てば歯垢が石灰化して「歯石」となり、さらに細菌の温床となります。歯石になると、もはや自宅の歯磨きでは取り除けません。そうして蓄積した細菌が悪臭を放つガスを発し、慢性的な口臭へとつながっていくのです。
奥歯・歯と歯の隙間は特に注意が必要
人間の口の中でも特に清掃が難しいのが「奥歯」と「歯と歯のすき間」です。奥歯は視認性も悪く、力加減や角度によっては十分にブラシが届かないことがあります。また、歯間はフロスや歯間ブラシを使わない限り、歯ブラシだけで汚れを取りきるのは困難です。
さらに、歯並びが悪いとこうした「磨きにくい箇所」が増え、全体的に口内の衛生レベルが下がってしまいます。とくに唾液の流れが滞りやすい下の奥歯の内側や、八重歯の裏側は、口臭の発生源になりやすい部位として知られています。
磨きにくいという小さな問題が、日々の積み重ねで「においの温床」となり、いつしか口臭として現れてしまう――。そんな悪循環を断つには、歯並びそのものを整え、磨きやすい口内環境を作ることが大切なのです。
噛み合わせの悪さが生む口臭リスク

歯並びだけでなく、「噛み合わせ」も口臭の大きな要因になることをご存じでしょうか。しっかりと噛めない状態が続くと、口の中ではさまざまな悪循環が起こり、知らず知らずのうちにニオイの元が増えてしまうのです。ここでは、噛み合わせの乱れがどのように口臭へつながるのかを具体的に解説します。
一部の歯に負担がかかり歯ぐきが弱る
噛み合わせに問題があると、咀嚼の力が特定の歯に集中してしまいます。本来、上下の歯は均等に接触し、全体で噛む力を分散する仕組みになっています。しかし、噛み合わせがズレていると一部の歯や歯ぐきに過剰な力がかかり、炎症を引き起こしやすくなります。
歯ぐきが傷んだり炎症を起こしたりすると、歯周病菌が繁殖しやすくなり、これが強い口臭の原因となります。歯周病由来の口臭は特有のにおいがあるため、自分で気づきにくく、まわりに指摘されて初めて自覚するケースも少なくありません。つまり、噛み合わせの悪さが「歯ぐきの不調」→「細菌の増殖」→「口臭」へとつながる連鎖を生むのです。
咀嚼不足で唾液が減少し、口が乾く
噛み合わせが悪いと、しっかりと咀嚼することができません。その結果、食べ物をよく噛まないまま飲み込んでしまう傾向が強くなります。咀嚼が不十分だと、唾液の分泌が促されず、口の中が乾燥しやすくなります。
唾液には、細菌の繁殖を抑える働きや、口内の汚れを洗い流す自浄作用があります。唾液が十分に出ていれば、ニオイの原因物質が洗い流され、口臭も抑えられます。しかし、噛む回数が減ることで唾液の量が不足し、乾燥した口腔内は細菌にとって格好の繁殖環境となり、結果的に口臭が強くなってしまうのです。
噛む力の偏りで炎症や知覚過敏も口臭の原因に
噛み合わせが乱れていると、咀嚼のたびに特定の歯や顎に負担がかかります。これが長く続くと、歯に微細なヒビが入ったり、歯の根元が削れて知覚過敏を引き起こしたりすることがあります。また、慢性的な刺激によって歯ぐきが下がり、露出した歯の根元に汚れがたまりやすくなるのも問題です。
このような部位には歯ブラシも当たりにくく、知らぬ間に細菌の温床となってしまうことがあります。さらに、炎症があるとそれ自体からも不快なにおいが出るため、歯ぐきや歯の不調がそのまま「口臭の発生源」となってしまうのです。
口臭対策だけでは改善しない理由

市販のマウスウォッシュや口臭タブレット、歯磨き粉など、さまざまな口臭対策グッズが出回っています。もちろんこれらは一時的なニオイの軽減には役立ちますが、根本的な改善にはつながらないことも多いのです。ここでは、口臭ケアだけでは乗り越えられない本当の原因とその限界について解説します。
マウスウォッシュでは根本原因は消せない
口臭が気になると、まず思いつくのがマウスウォッシュやスプレータイプの消臭剤。使用直後はスッキリとした清涼感があり、一時的にニオイを抑えることは可能です。しかし、これはあくまで上から香りをかぶせているだけであり、根本的に細菌の繁殖や歯垢の除去ができているわけではありません。
むしろアルコールを含むタイプの洗口液は、口内を乾燥させてしまい、かえって口臭を悪化させるケースもあるため注意が必要です。根本的な解決には、ニオイの元となる「磨き残しのない口内環境」そのものを作り直す必要があります。
舌磨き・ブレスケアも一時的な対処にすぎない
舌苔(ぜったい)と呼ばれる、舌の表面に付着した白っぽい汚れも、口臭の原因として知られています。これに対する対策として舌磨きがありますが、力を入れすぎると舌を傷つけてしまい、かえって炎症や菌の繁殖を招くこともあります。また、タブレットやミントなどのブレスケア製品も、ニオイを一時的にごまかすための手段であり、細菌や歯垢そのものに作用するものではありません。
これらの対策は応急処置としては有効でも、毎日続けなければならない、あるいは根本的な原因が放置されるというリスクもあるのです。
「磨ける歯並び」でなければ清潔は保てない
どれだけ丁寧にケアをしていても、歯並びが乱れていると物理的にブラシが届かない部分が出てきます。特に叢生(ガタガタの歯並び)や歯が傾いて生えている部位では、フロスや歯間ブラシを使っても清掃が難しいことがあります。こうした「磨けない場所」は、細菌の温床となり、いくら表面をきれいにしても口臭が残る原因になってしまうのです。
つまり、根本的に口臭を改善するには、「磨きやすい歯並び」に整えることが最も現実的で効果的な対策となります。これは口臭だけでなく、虫歯や歯周病の予防にもつながるため、長期的な口腔環境を整える意味でも重要なアプローチといえるでしょう。
口臭対策、ひとりで悩んでいませんか?気になる症状がある方は、お早めに専門医へ。
インビザラインが口臭予防に適している理由

歯並びを整える矯正治療の中でも、近年注目されているのが「インビザライン」です。透明なマウスピース型矯正装置であるインビザラインは、見た目に目立ちにくいだけでなく、実は口臭予防の観点でも非常に理にかなった治療方法なのです。ここでは、インビザラインがなぜ口臭予防に適しているのか、その理由を3つの視点から解説します。
取り外せるから毎日の歯磨きがしやすい
インビザライン最大の特徴は「取り外しができる」という点です。ワイヤー矯正の場合、装置が固定されているため、歯磨きがしづらく、どうしても磨き残しが増えがちです。一方、インビザラインは食事や歯磨きの際に簡単に外せるため、装置を気にせず普段どおりにブラッシングやフロスが行えます。
これは口臭予防にとって非常に大きなメリットです。歯と歯の間、奥歯の裏、歯ぐきとの境目など、細かい部分までしっかり磨けることで、口内に残る細菌や食べかすの量が圧倒的に減少します。つまり、インビザラインを選ぶことで、矯正治療中も清潔な口内環境をキープしやすくなるのです。
マウスピースが歯の位置を整え清掃性アップ
歯並びが整っていないと、どれだけ丁寧に磨いてもブラシが届かない場所が生まれやすくなります。インビザラインによる矯正は、少しずつ歯の位置を動かし、全体を理想的な歯列に近づけていく治療法です。その結果、デコボコだった歯並びが整い、自然と磨きやすい口の中へと変わっていきます。
清掃性が向上すれば、口臭の原因である歯垢や細菌の蓄積を抑えることができます。特に、歯と歯のすき間や歯ぐきとの境目など、普段から磨きにくい部位にアクセスしやすくなることで、より衛生的な状態を維持できるのです。
ワイヤー矯正に比べて口腔衛生が保ちやすい
従来のワイヤー矯正では、金属のブラケットやワイヤーに食べ物が絡まりやすく、清掃が難しいというデメリットがありました。また、固定装置の周囲に汚れが溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まることも問題視されています。
インビザラインはこうした固定装置を使用しないため、そもそも「汚れが溜まりやすい構造」がありません。毎日マウスピースを外してしっかり歯磨きができる点、マウスピース自体も洗浄できる点から、治療中でも高い口腔衛生を保ちやすいのが特徴です。
また、マウスピースは定期的に新しいものに交換されるため、菌の温床となる心配も少なく、常に清潔な状態を維持できます。こうした理由から、口臭予防の観点でもインビザラインは非常に有効な選択肢といえるのです。
インビザラインで整う口臭に強い口内環境

口臭を根本から改善するためには、原因を取り除くだけでなく、再発しにくい「清潔な口内環境」をつくることが重要です。インビザラインによる歯列矯正は、単に見た目を整えるだけでなく、口臭が起きにくい状態を育む予防的な役割も果たします。ここでは、インビザラインがどのようにして「口臭に強い口内環境」を整えていくのかを解説します。
歯の重なりがなくなり歯間清掃がスムーズに
ガタガタした歯並びは、歯と歯が重なっている箇所が多く、どうしてもブラッシングでは磨き残しが出やすくなります。特に歯間部は歯ブラシの毛先が届きにくく、食べかすや歯垢が蓄積しやすいため、口臭の温床となることが少なくありません。
インビザラインで歯並びが整うと、歯と歯の間に適切なスペースが生まれ、フロスや歯間ブラシが使いやすくなります。また、歯面全体が均一に見えるようになることで、ブラッシングの精度も上がりやすく、日常的なセルフケアの質が格段に向上します。こうして「清掃性の高い歯並び」が、ニオイの元をつくらせない環境を支えてくれるのです。
歯列の整備で唾液が行き届きやすくなる
歯並びが悪いと、唾液の流れが偏ったり、特定の部位に唾液が届きにくくなったりします。唾液は口腔内の汚れを洗い流し、菌の繁殖を抑える働きを持つため、唾液が届かない部位では細菌が増殖しやすく、口臭の原因となるリスクが高まります。
インビザラインで歯列を整えることにより、咀嚼時の力のバランスが均等になり、自然と唾液の分泌も促されるようになります。口腔内のすみずみまで唾液が行き渡ることで、自浄作用が発揮されやすくなり、ニオイを発する物質の蓄積を抑制する効果が期待できます。
口臭の原因を根本から減らす予防型の矯正
インビザラインは、治療中の口腔内清掃をしやすくするだけでなく、治療後のにおいにくい口内環境づくりにもつながる矯正方法です。歯並びが整えば、細菌がたまりにくく、唾液の流れもスムーズになり、歯周病や虫歯のリスクが軽減されます。これらはすべて、口臭の予防にも直結する要素です。
さらに、見た目の改善によって自信が持てるようになり、積極的に人と話す機会が増えることで、会話中の口臭への不安が軽減されるという心理的効果も得られます。単なる治すための矯正ではなく、再発させないための矯正として、インビザラインは長期的な口臭予防に大きく貢献してくれるのです。
インビザライン矯正について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
口臭だけじゃない、歯並び改善の健康メリット

歯並びを整える目的は、見た目を美しくすることや口臭を防ぐことだけにとどまりません。実は、歯列の改善は全身の健康やQOL(生活の質)にも深く関係しています。ここでは、インビザラインなどによる歯並び改善がもたらす、口臭以外の健康面でのメリットに焦点を当ててご紹介します。
虫歯・歯周病リスクも大幅にダウン
歯並びが乱れていると、歯ブラシの届かない場所が多くなり、どうしても歯垢や食べかすが残りがちです。これらが蓄積すると、虫歯菌や歯周病菌が繁殖しやすい環境が生まれ、虫歯や歯周病のリスクが高まります。これらの疾患は、進行すると歯を失うだけでなく、強い口臭の原因にもなります。
一方で、歯並びが整っていると、歯の表面が均一になり、日々の歯磨きでも効率的に汚れを落とすことができます。歯間ブラシやデンタルフロスも使いやすくなり、清掃性が大幅に向上。結果として、虫歯や歯周病の予防につながり、歯の健康寿命を延ばすことができるのです。
噛み合わせ改善で顎関節や姿勢にも好影響
噛み合わせが乱れていると、顎の動きに偏りが生じ、顎関節への負担が増します。これが慢性化すると、顎関節症や肩こり、頭痛など、口腔外の不調にもつながっていきます。さらに、正しい噛み合わせができていない状態では、姿勢のバランスにも影響が及び、身体のゆがみを引き起こすこともあります。
歯並びを整えることで咀嚼のバランスが整い、顎の動きが自然になります。それにより顎関節への負担が軽減され、顔や首、肩の緊張もやわらぎやすくなります。これは一見、口臭とは関係がないように思われがちですが、全身のバランスが整うことでストレスも軽減され、結果的に唾液分泌が促進されるなど、間接的に口臭予防にもつながっていくのです。
全身の健康維持に関わるお口のトータルケア
近年、「お口の健康が全身の健康とつながっている」という考え方が医療現場でも定着してきています。たとえば、歯周病は糖尿病や心疾患、認知症などの全身疾患と関連があるとされており、口腔ケアが全身の病気予防にも関係しているという研究結果も報告されています。
歯並びを整えることで、日々の口腔ケアがしやすくなり、細菌の繁殖を防ぎやすくなります。その結果、歯周病や虫歯のリスクが下がり、健康な口内環境を維持しやすくなります。これは、単に口臭を予防するためだけではなく、体全体の健康を支える「第一歩」と言えるでしょう。
実際の症例をご覧ください。
歯並びと口臭、こんな人は要注意!

「毎日歯を磨いているのに、なぜか口臭が気になる…」「人と話すときに口元が気になる…」そんなお悩みを抱えている方は、もしかすると歯並びが原因かもしれません。ここでは、歯並びと口臭の関係から、特に注意が必要なタイプや生活習慣の傾向を持つ人を具体的にご紹介します。
いつもマスクの中のニオイが気になる人
マスク生活が日常になったことで、自分の口臭に気づく機会が増えたという人は少なくありません。「マスクをしていると、自分の口のにおいが気になる」「朝起きた直後、マスク内が不快」と感じたことはありませんか?
それは、口内にニオイの元が蓄積しているサインかもしれません。
とくに、歯並びが悪いとブラッシングが行き届かず、磨き残しや歯垢が増えやすくなります。これが口臭の原因物質を発生させ、マスクの中でこもったニオイとして感じやすくなるのです。もし心当たりがある方は、歯並びも口臭原因のひとつとして見直す価値があります。
舌苔やネバつきが気になりやすい人
舌の表面に白っぽい汚れ(舌苔)が溜まりやすい、口の中がネバネバする――こうした症状がある方も要注意です。舌苔は、食べかすや細菌、口内の老廃物が舌にこびりついたもので、強い口臭の原因になります。
歯並びが悪いと咀嚼が不十分になり、唾液の分泌が減ってしまうため、口内の自浄作用がうまく働かなくなります。その結果、舌の清掃も不十分になり、舌苔がたまりやすくなってしまうのです。また、ネバつきは乾燥した口腔環境に起きやすく、やはり歯列不正や噛み合わせの乱れによって唾液が出にくくなることが関係しています。
見た目以上に清掃性の悪さが気になる人
パッと見た印象では「歯並びがそこまで悪くない」と思っていても、実際に磨いてみると「どうしてもこの部分が磨きにくい」「フロスが入りにくい」など、清掃のしづらさを感じる人は要注意です。
自覚症状が少なくても、日々の磨き残しが蓄積され、知らないうちにニオイの元となってしまっていることもあります。
特に、八重歯や奥歯の傾き、歯のねじれなどがあると、局所的に歯ブラシの届きにくいエリアができてしまいます。こうした「見た目ではわかりにくいリスク」を抱えている方こそ、口臭の原因が歯並びにある可能性を疑うべきタイミングかもしれません。
10. まずは歯並びを知ることから始めよう

口臭の原因を探るうえで、歯並びの影響は見逃せません。「見た目が気になるから」という理由だけでなく、「磨きやすさ」や「口腔内の清潔さ」といった目に見えない健康にまで影響を与えるのが歯並びです。まずは自分の歯列の状態を正しく知ることから、口臭予防の第一歩が始まります。
自分の歯並びの状態を客観的に把握する重要性
鏡で歯を見たときに「なんとなくデコボコしている」「前歯だけ少し出ている」などと感じても、専門的に見なければ清掃性のリスクや噛み合わせの問題は把握しきれません。特に、奥歯の傾きや、噛み合わせのズレ、上下の歯の関係性といった要素は、専門の検査でなければ確認できないことがほとんどです。
自分では問題ないと思っていた歯並びも、実は口臭の原因となる磨けないゾーンを多く抱えているかもしれません。まずは一度、歯列やかみ合わせのチェックを受けることで、日常的なケアでは見えなかった課題が明確になります。
清掃しやすい歯列が未来の口腔環境を変える
歯並びを整えることで得られる最も大きなメリットのひとつが、「清掃しやすくなること」です。どんなに高機能な歯ブラシや洗口液を使っていても、物理的に磨けない場所があると、その部分に細菌は必ず残ってしまいます。
インビザラインのような矯正治療によって歯列が整えば、ブラッシングの効率が上がり、すみずみまで清掃できるようになります。結果として、虫歯・歯周病・口臭といったトラブルのリスクを同時に減らすことが可能になり、将来にわたって健康な歯と口腔環境を保ちやすくなるのです。
清潔なお口をめざす第一歩は「整った歯並び」から
「口臭の原因は歯並びだった」――そう気づけることが、改善への第一歩です。毎日のケアに限界を感じていたり、マスクの中のにおいが気になっていたりするなら、まずはご自身の歯並びを見つめ直してみてください。
矯正治療は、見た目を整えるだけでなく、機能面や衛生面にも大きく貢献します。特にインビザラインのような目立たず快適に進められる選択肢は、口臭の悩みを根本から解決し、長期的に清潔な口内環境を育ててくれます。
「見えない部分の清潔さ」こそが、あなたの自信につながる――そのための手段として、歯並びの改善を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。
気になる症状がある方は、お早めに専門医へ。
神奈川県伊勢原市の
見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)
『 つじむら歯科医院 伊勢原 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士