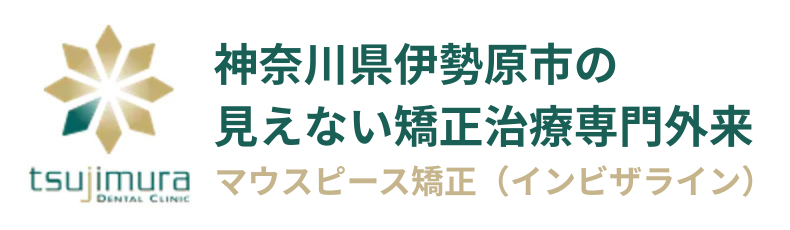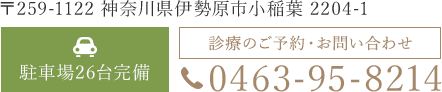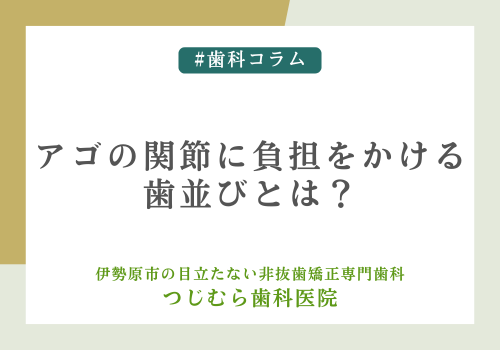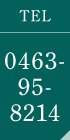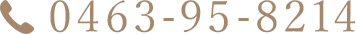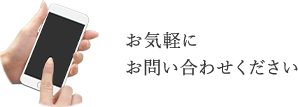「口を開けるとアゴがカクッと鳴る」「朝起きるとアゴがだるい」
そんな小さな違和感を感じたことはありませんか?その症状、実は歯並びや噛み合わせの問題が原因となって、アゴの関節に負担がかかっているサインかもしれません。放っておくと顎関節症に進行することもあるため、早めの対処が大切です。
本記事では、アゴに負担をかける歯並びの種類や原因、さらに予防・改善のための方法をわかりやすく解説します。
1. アゴが鳴る・だるい…それ、歯並びのせいかもしれません

日常生活の中でふと感じるアゴのだるさやカクカクと鳴る音。実はそれ、放置すると深刻なトラブルにつながる「顎関節症」のサインかもしれません。まずは歯並びとの関係に注目してみましょう。
顎関節症と歯並びの意外な関係
「口を開けるとアゴがカクカク鳴る」「アゴのあたりがだるい・疲れやすい」そんな症状に悩まされている方はいませんか?それ、もしかしたら顎関節症(がくかんせつしょう)のサインかもしれません。顎関節症とは、アゴの関節やその周辺の筋肉に異常が起こり、口の開閉がスムーズにいかなくなったり、痛みを感じたりする状態のことです。近年では、子どもや若年層にもこうした症状が増えてきており、原因のひとつとして「歯並びや噛み合わせの問題」が注目されています。
アゴの関節は、ものを噛むたびに複雑な動きをしています。本来であれば上下の歯がバランスよく噛み合い、左右のアゴの筋肉にも均等に力がかかる仕組みです。しかし、歯並びにゆがみや偏りがあると、噛むたびに特定の方向に無理な力が加わり、関節や筋肉に大きな負担をかけてしまうのです。
痛みや違和感を放置するとどうなる?
最初は「ちょっと音がするだけ」「たまに疲れる程度」と見過ごされがちな顎関節の不調。しかし放置してしまうと、症状は徐々に悪化していきます。開口障害(口が開きにくくなる)、関節のロック(途中で引っかかる)、痛みの慢性化などが進行する可能性があり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
また、アゴの不調は食事だけでなく、発音や睡眠の質にも影響を与えることがあります。さらに、関節のストレスが肩や首、頭部にまで波及し、頭痛・肩こり・耳鳴りといった全身症状につながるケースもあるため、早めの対応が大切です。
顎関節の負担に気づきにくい人の特徴
「自分ではまったく気づかなかったのに、検診で指摘された」というケースも少なくありません。特に、以下のような方は要注意です。
・歯ぎしり・食いしばりの癖がある
・寝起きにアゴが重だるい
・片側だけで物を噛む習慣がある
・顔のゆがみや、笑顔の左右差が気になる
こうした習慣は、歯並びや噛み合わせに悪影響を与え、結果的にアゴの関節に慢性的なストレスを与える原因となります。
今は痛みがなくても、「なんとなく気になる」サインがあれば、それはお口やアゴからのSOSかもしれません。放置せず、まずは歯科医院でのチェックを受けてみることが大切です。
顎の不調、見逃さずに。まずは無料カウンセリングへ
2. アゴの関節に負担をかける歯並びの種類とは

見た目では判断しづらい歯並びの乱れが、アゴの関節に大きな影響を与えていることがあります。どのような噛み合わせが負担となるのか、具体例を挙げながらご紹介します。
顎関節にストレスを与える噛み合わせとは?
歯並びと聞くと、多くの方が「見た目」の問題を思い浮かべるかもしれません。しかし実は、歯並びのゆがみは見た目だけでなく、アゴの関節、つまり顎関節にも大きな影響を与えます。噛み合わせが悪いと、上下の歯がしっかりと噛み合わず、アゴの関節がスムーズに動かなくなり、噛むたびに特定の関節や筋肉に負担が集中してしまうのです。
本来、噛み合わせとは前歯・奥歯すべてが連動し、左右のアゴの筋肉がバランスよく使われる状態が理想です。しかし、そのバランスが崩れると、顎関節が無理な位置に引っ張られたり、関節内の軟骨(関節円板)がズレることで、関節の鳴音や痛みが発生します。
見た目ではわからない機能的な問題
歯並びの異常と聞くと、見た目でわかる「出っ歯」や「ガタガタの歯並び(叢生)」を思い浮かべがちですが、実は一見きれいに見える歯並びでも、アゴの関節に負担がかかっている場合があります。たとえば、以下のようなタイプは、見た目では判断しにくい機能的な問題を含んでいます。
・交叉咬合(こうさこうごう):左右で上下の歯の噛み合わせがすれ違っている状態。片側に負担が集中しやすい。
・開咬(かいこう):前歯が噛み合わず、奥歯だけで噛んでいる状態。アゴの動きに歪みが出やすい。
・過蓋咬合(かがいこうごう):上の前歯が下の歯を深く覆っている状態。アゴの動きが制限される。
このような噛み合わせは、関節だけでなく咀嚼効率にも悪影響を及ぼし、消化不良や顎筋の疲労を引き起こす原因になります。
子どものうちに気づきたい歯並びのクセ
さらに注意したいのが、成長期の子どもの歯並び。子どもは顎の骨が柔らかく、舌や唇、頬の筋肉の使い方に影響を受けやすいため、ほんの些細なクセでもアゴに負担がかかる歯並びに繋がる可能性があります。
・口呼吸やポカン口:舌が下がり、アゴの発達が遅れる
・指しゃぶりや頬杖:前歯の傾斜やアゴの左右差につながる
・片側噛みの習慣:筋肉のバランスが崩れ、関節への偏った圧力がかかる
これらの習慣が続くと、顎関節の片側だけが過剰に使われるようになり、将来的に関節のズレや慢性痛のリスクが高まります。早期に発見・対処することで、顎関節へのダメージを未然に防ぐことができるのです。
3. 開咬・受け口・出っ歯がアゴに与える影響

一見わかりやすい歯並びの異常も、アゴにかかる負担という観点で見ると深刻です。ここでは、特に影響が大きい3つの歯並びタイプについて詳しく解説します。
開咬(かいこう)で起こるアゴの不調
「開咬」とは、口を閉じたときに奥歯だけが当たり、前歯が噛み合わず隙間ができてしまう状態を指します。前歯で食べ物を噛み切れず、奥歯にばかり負担がかかるため、アゴの関節や筋肉が酷使される傾向があります。特に、硬いものを噛むときや長時間の会話の際にアゴの疲れや痛みを感じる方は、開咬の可能性を疑ってみるべきです。
また、開咬の人は無意識のうちに口呼吸になっているケースが多く、これが舌の位置や筋肉バランスに影響を与え、アゴの関節を不安定にさせてしまう原因にもなります。顎関節症の初期段階では「口を開けると音が鳴る」「アゴがだるい」といった症状が多く見られ、放置すると痛みや開口障害に進行してしまうリスクもあります。
受け口(下顎前突)がもたらすズレと緊張
受け口(下顎前突)は、下アゴが前に突き出ている状態を指します。見た目にも特徴的ですが、問題は見た目以上に「アゴの位置のズレ」にあります。下アゴが本来あるべき位置よりも前に出ることで、関節部分が本来の軌道で動けなくなり、余計な緊張やストレスがかかってしまうのです。
特に、受け口の方は食事の際に「ずらして噛む」「左右どちらかに偏って噛む」など、無意識のうちに代償動作を取ってしまうことがあり、関節に不自然な力がかかる原因となります。こうした偏りは、関節内部の軟骨(関節円板)にも影響を及ぼし、将来的に関節のズレや慢性痛、関節音の原因にもなりかねません。
受け口(下顎前突)について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
出っ歯(上顎前突)が生む過緊張状態
出っ歯(上顎前突)は、上の前歯が前方に突出している歯並びのことです。この状態では、前歯が正しく噛み合わないため、奥歯やアゴの筋肉に過度な力が加わるようになります。特に、無意識のうちに上下の歯を食いしばる癖がある人は、常にアゴの筋肉が緊張状態にあり、顎関節への負担が大きくなります。
また、出っ歯の人は唇が閉じづらく、口が開きやすい傾向があります。そのため、口呼吸になりやすく、舌の位置が下がり、アゴの筋肉や関節にかかるバランスが乱れる原因となります。睡眠中の無意識な食いしばりや歯ぎしりが重なることで、朝起きたときにアゴの痛みや重だるさを感じることも少なくありません。
出っ歯(上顎前突)について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
4. アゴの関節は「噛み合わせバランス」が命

噛むという行動には、関節や筋肉の繊細なバランスが必要です。片側噛みや食いしばりのクセがアゴに与える影響と、バランスの重要性を見ていきましょう。
正常な咬合と関節の理想的な位置関係
私たちが毎日行っている「噛む」という動作は、見た目以上に繊細なバランスの上に成り立っています。上下の歯がしっかりと噛み合い、左右のアゴの筋肉や関節が対称に動くことで、口腔機能は正常に保たれます。噛み合わせ(咬合)のバランスが取れている状態では、アゴの関節=顎関節(がくかんせつ)に無理な力がかかることはなく、筋肉や骨にとっても自然な動きが維持されます。
しかし、噛み合わせにズレがあると、アゴの関節が本来のポジションから逸脱し、筋肉や関節内構造にストレスがかかり始めます。これが積み重なることで、顎関節症の初期症状(音が鳴る・だるさ・痛みなど)が現れやすくなるのです。
左右どちらかに偏った噛み癖の影響
普段の食事や会話で、片側だけで噛んでいる自覚はありませんか?この「片側噛み」のクセは、知らず知らずのうちに噛み合わせのバランスを崩し、アゴに大きな負担をかける原因となります。片側だけの筋肉が過剰に使われると、もう一方の筋肉が衰え、顔のゆがみや関節の片側への偏位が起こりやすくなります。
また、偏った咀嚼は関節円板(顎関節内のクッション役)を一方向に引き込みやすくなり、「カクカク音がする」「引っかかる」といった違和感のもとになることもあります。関節にかかる圧力が不均等になると、筋肉が常に緊張状態にさらされ、慢性的なアゴの疲労や痛みへとつながっていきます。
食いしばり・片側咀嚼が引き起こすゆがみ
日常的なストレスや集中時に無意識に「食いしばっている」方も多いのではないでしょうか。特に睡眠中の食いしばりや歯ぎしりは、アゴの筋肉に非常に強い力をかけ、噛み合わせのバランスを崩す大きな要因です。
さらに、食いしばりや片側咀嚼を繰り返すことで、アゴの位置そのものがズレてしまい、関節が歪んだ位置で固定されてしまうこともあります。このような状態が続くと、筋肉だけでなく骨格レベルでの不調が生じ、矯正治療が難しくなるケースもあるため、早めの対処が必要です。
5. 成長期の歯並びがアゴの将来を左右する

子どものアゴは発達段階にあり、歯並びや癖が将来に大きな影響を与えます。早期に適切な矯正を行うことで、アゴの健康を守る土台が築けます。
子どもの顎関節は未成熟で影響を受けやすい
成長期の子どものアゴは、まだ骨格が柔らかく発達途中の段階にあります。この時期のアゴの成長は、遺伝的な要素だけでなく、噛み方や歯並び、舌の使い方といった日常的な習慣に大きく影響を受けます。つまり、「子どもの歯並び」は、見た目だけの問題ではなく、将来のアゴの関節機能や顔の形にも直結する重要なファクターなのです。
例えば、上の前歯が噛み合わない「開咬」や、下あごが前に突き出る「受け口」などは、アゴの関節に無理な動きを強いる原因になります。関節がズレたまま骨格が形成されると、大人になってから顎関節症や顔の非対称、慢性的な肩こり・頭痛などを引き起こす可能性も高まります。
小児期の矯正が関節への予防策になる理由
子どものうちに噛み合わせの異常に気づき、適切なタイミングで矯正を始めることは、アゴの関節にとっても非常に大きなメリットがあります。矯正と聞くと「見た目を整えるもの」と思われがちですが、実は歯やアゴの機能を正しく育てるための重要な医療的アプローチでもあります。
インビザライン・ファースト(小児用マウスピース矯正)は、成長途中のアゴの発達をコントロールしながら、将来的な関節への負担を軽減することが可能です。ワイヤー型の矯正に比べて痛みが少なく、取り外しもできるため、日常生活への影響が少ないのも大きな魅力です。さらに、清掃性が高いため、虫歯や歯肉炎のリスクも抑えられ、健康的な口腔環境を維持しやすいのが特徴です。
放置された悪習癖(口呼吸・舌癖)と関節リスク
子どもの歯並びに影響を与えるのは、骨格や遺伝だけではありません。実は、「口呼吸」「舌で歯を押すクセ(舌癖)」「頬杖」「指しゃぶり」などの悪習癖が、歯並びやアゴの成長に大きな影響を与えます。これらの習慣が続くと、アゴの筋肉の使い方に偏りが生じ、顎関節の発育がアンバランスになります。
特に口呼吸の習慣は、舌が正しい位置(上顎)に置かれないため、上アゴの横幅が狭くなり、歯が重なったり、噛み合わせがずれてしまったりする原因になります。こうした歪みがアゴに蓄積されていくことで、成長後に顎関節症のリスクが高まるのです。
6. アゴが「カクカク鳴る」…そのサインを見逃さない

アゴから音が鳴るのは、顎関節の構造に問題が起きているサインかもしれません。早期のセルフチェックと対処が、重症化を防ぐ鍵となります。
関節ディスクのズレが生むクリック音とは
「口を開けるとアゴがカクンと鳴る」「閉じるときに音がする」――そんな経験はありませんか?このクリック音の正体は、顎関節の中にある「関節円板(ディスク)」のズレが関係しています。関節円板とは、アゴの骨と骨の間にあるクッションのような存在で、咀嚼運動の際にスムーズな動きを助ける役割を持ちます。
しかし、噛み合わせのズレや歯並びの問題によって関節に偏った力がかかり続けると、このディスクが正常な位置から前方にズレてしまいます。開閉時にズレたディスクが一時的に戻ることで「カクッ」という音が鳴るのです。初期の段階では痛みを伴わないことも多く、つい見逃してしまいがちですが、これは顎関節症の予兆として非常に重要なサインです。
口の開閉時に違和感を感じたら要注意
音だけでなく、「開けにくい」「閉じにくい」「途中で引っかかる」といった開閉時の違和感を感じた場合、それは関節内部で何らかの異常が進行している可能性があります。中でも、関節が引っかかってしまい、口が指2本分ほどしか開かなくなる「開口障害」は注意が必要です。
このような症状は、クリック音の段階を過ぎて関節ディスクが戻らなくなる状態に近づいていることを示しています。放置すると、関節内部で炎症が進み、強い痛みやアゴの変形を引き起こすこともあるため、早期の対応が求められます。
初期のサインを見逃さないセルフチェック法
日常生活の中で、自分のアゴの状態を簡単に確認するセルフチェック法を知っておくことはとても大切です。以下の項目にひとつでも当てはまる場合は、顎関節に異常がある可能性があります。
・口を開けると左右にブレる
・口を大きく開けられない(指3本縦に入らない)
・開閉時に音がする
・噛むとアゴが疲れる・痛む
・起床時にアゴが重だるい
これらのサインは、顎関節症の初期段階によくみられる症状です。特に「音が鳴るだけで痛くないから大丈夫」と放置しがちですが、実際にはすでに関節内部に負担がかかっており、将来的なリスクが高まっている可能性があります。
インビザライン矯正は、こうした関節のストレスの原因となる噛み合わせや歯並びのズレを、負担をかけずに整えていく治療法です。痛みや不調を感じる前に、関節の状態をチェックし、必要があれば専門的な診断を受けることが大切です。
実際の症例をご覧ください。
7. 慢性的な頭痛・肩こりは歯並び由来かもしれない

原因不明の肩こりや頭痛に悩まされている方は、実は噛み合わせのズレが関係しているかもしれません。歯並びと全身の筋肉バランスの関係に迫ります。
噛み合わせと姿勢バランスの深い関係
「いつも肩がこる」「頭痛が続いている」そんな症状の原因が、まさか歯並びや噛み合わせにあるとは思いもよらない方も多いかもしれません。実は、口の中の状態と全身の筋肉のバランスは密接に関係しており、噛み合わせのズレがアゴの関節だけでなく、頭・首・肩の筋肉にまで影響を及ぼすケースが少なくないのです。
噛み合わせが悪い状態では、咀嚼や会話のたびにアゴの筋肉に偏った力が加わります。アゴを支える筋肉は首や肩ともつながっているため、アゴの動きが不安定になることで、周囲の筋肉が無理にバランスを取ろうとし、結果的に肩や首のこりを引き起こすのです。長時間のデスクワークやスマホの使用で姿勢が悪い方は、さらにその負担が増す傾向にあります。
顎関節の緊張が全身に与える影響
噛み合わせによる筋肉の緊張が慢性化すると、血流の滞りや神経の圧迫が起こり、慢性的な頭痛や倦怠感、目の奥の痛みなどにつながることもあります。特に「こめかみのあたりがズキズキする」「後頭部に鈍い痛みを感じる」などの症状は、アゴの関節や咀嚼筋からくる可能性があるといわれています。
また、アゴのズレが原因で体の左右の筋肉バランスが崩れると、肩の高さが変わったり、骨盤のゆがみにつながったりすることもあります。たかが歯並びと思われがちですが、そのズレが全身のバランスに波及していくケースは意外と多く、歯科・整形外科・整体などでも注目されている分野です。
歯科医院でできる全身症状の原因探し
「頭痛や肩こりで病院に行ったけれど、原因がはっきりしない」とお悩みの方にこそ、一度噛み合わせのチェックをおすすめします。歯科医院では、顎関節の動き・歯の接触状態・筋肉の緊張などを総合的に評価し、不調の原因が口腔由来かどうかを見極めることができます。
特にインビザライン矯正では、見た目だけでなく機能面にも配慮した治療が可能です。無理な力をかけず、徐々に正しい噛み合わせへ導くことで、アゴの関節や筋肉にかかる負担を軽減し、全身症状の緩和にもつながる可能性があります。
肩こりや頭痛は、身体の「使い方」だけでなく、「噛み方」に原因があることもあるのです。原因不明の不調が続いている方は、一度お口の中からのアプローチを検討してみてはいかがでしょうか。
8. インビザラインでアゴの関節にやさしい矯正ができる理由

アゴにやさしい矯正治療として注目されるインビザライン。なぜ関節に負担が少ないのか、清掃性や力のかかり方までその特長を詳しく解説します。
歯並びを整えることで清掃しやすくなる
アゴの関節に負担をかける大きな要因のひとつが「噛み合わせのズレ」です。このズレは、上下の歯が正しくかみ合わないことで、関節の動きにゆがみを生み、筋肉や関節内部の組織に過剰な力を加える原因となります。インビザラインは、この噛み合わせのズレを徐々に整え、関節の動きをスムーズにすることで、アゴへの負担を軽減する治療法です。
特に注目すべきは、歯並びが整うことでブラッシングがしやすくなり、清掃性が向上する点です。汚れがたまりにくくなることで、歯周病や炎症による関節への影響を予防しやすくなります。歯ぐきや歯の周囲組織が健康であれば、関節にかかる外的ストレスも減少し、顎関節の安定性にも良い影響を与えます。
正しい噛み合わせでアゴへの負担も軽減
インビザラインは、精密な3Dシミュレーションを活用して治療計画を立てるため、噛み合わせのバランスまで考慮した歯の移動が可能です。一般的な矯正では見た目の歯列だけを重視しがちですが、インビザラインでは、咀嚼時のアゴの動きや歯の接触面も考慮され、関節にやさしい力の配分が設計されています。
たとえば、前歯だけでなく奥歯のかみ合わせまでを最終位置として正確に調整することで、咀嚼時の力が一部の歯や筋肉に集中するのを防ぎます。その結果、関節にかかる圧力が分散され、慢性的な緊張や炎症を防ぐことができます。
さらに、インビザラインのマウスピースは1日20〜22時間装着することで、自然とアゴの動きを整えるトレーニングにもなります。噛む位置や筋肉の使い方が次第に改善され、関節が理想的な位置に安定するようになるのです。
矯正中も衛生管理しやすいから安心
ワイヤー矯正と比べて、インビザラインは着脱ができるため、食事や歯みがきの際にストレスを感じにくいという特徴があります。この点は、顎関節にとってもメリットがあります。口腔内の清掃性が高い状態を保つことは、歯肉の健康維持に直結し、結果的に咀嚼機能やアゴの運動の安定にもつながります。
また、痛みや違和感が少ないという点も見逃せません。強い力で一気に歯を動かすのではなく、段階的かつやさしい力で矯正が進むため、アゴの関節や筋肉に過度なストレスをかけず、自然な変化を促すことが可能です。
インビザライン矯正について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
9. 顎関節に不調があってもインビザラインはできるのか?

アゴに不調を抱えている方でも、状態によってはインビザラインが可能です。治療の可否や医師選びのポイントについて丁寧にご説明します。
歯科医の判断によっては矯正可能なケースも多い
「アゴがカクカク鳴る」「口を開けると痛みがある」といった症状を抱える方の中には、「こんな状態で矯正治療なんてできるの?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。結論から言えば、顎関節に不調があっても、状態によってはインビザライン矯正は可能です。ただし、開始にはいくつかの大切な条件と事前の診断が必要になります。
まず確認すべきは、現在の顎関節の状態が「安定しているかどうか」です。痛みや炎症が強く出ている急性期には、無理に歯を動かすことで症状が悪化する可能性があるため、矯正治療よりも先に関節の治療や管理を優先します。しかし、症状が軽度であったり、すでに治療を終えて安定している場合は、インビザラインでの矯正が可能となることが多いのです。
歯科医院の「診断力」と「連携体制」が重要
顎関節症を抱えたままインビザラインを開始する場合、何よりも重要なのは精密な咬合診断と、関節を考慮した治療計画の立案です。マウスピース矯正は非常に精度の高い設計が可能な分、計画通りに歯が動くように設計されているため、アゴにかかる力の方向や噛み合わせの調整がしっかり管理されていなければ、かえって関節の症状が悪化するリスクもゼロではありません。
そのため、顎関節に不安がある場合は、「インビザラインに詳しいだけでなく、顎関節の診断にも長けた歯科医師」に相談することが大切です。医院によっては、顎関節症の専門医や口腔外科と連携を取りながら進められるところもあり、安心して治療を受けられる体制が整っているかがポイントとなります。
状態が安定すれば、むしろ矯正が予防につながることも
興味深いことに、噛み合わせが整うことでアゴの不調が改善されるケースもあります。顎関節のトラブルは、偏った咀嚼や歯並びのゆがみが原因となっていることが多く、インビザラインによってかみ合わせが均等に整うことで、関節の負担が軽減され、症状が緩和される可能性もあります。
ただし、これはあくまで「状態が安定している」「歯科医の管理のもとで進める」という前提があっての話です。自己判断や、噛み合わせに無関心な医院での矯正は、症状の悪化リスクも伴うため注意が必要です。
10. 歯並びとアゴの健康、両方を守るには

歯並びの美しさだけではなく、アゴの機能まで考慮した治療こそが本質的な矯正。両方をバランスよく整えることで、口腔と全身の健康を守れます。
歯並びと顎関節、どちらか一方では不十分
「見た目の歯並びさえ整えば、それで十分」と考えてしまいがちですが、実際の矯正治療では歯並びとアゴの関節機能の両方をバランスよく整えることが本質的なゴールです。たとえば、見た目にはきれいに並んでいるように見えても、噛み合わせの高さがズレていたり、特定の歯だけが強く当たっていたりすると、アゴの筋肉や関節に負担がかかり、将来的に顎関節症や咀嚼障害の原因となってしまいます。
逆に、関節の状態だけが安定していても、歯列が乱れていれば清掃性が悪くなり、虫歯や歯周病のリスクが高まり、口腔内全体の健康が損なわれてしまうのです。つまり、機能と見た目、両方をバランスよく整えることこそが、長期的な健康維持につながるのです。
インビザラインは「トータルバランス矯正」
インビザラインは、単に歯を並べるだけの治療ではありません。コンピューターによる3Dシミュレーションを活用することで、上下の噛み合わせ、アゴの動き、歯の傾きまで総合的に設計された治療計画が可能です。そのため、歯並びだけでなく、咀嚼機能やアゴの関節の安定性にまで配慮した矯正が実現できます。
さらに、インビザラインは1枚のマウスピースごとの移動量がとても小さく設定されているため、筋肉や関節に過剰な力をかけず、少しずつ調和の取れた状態へと導いてくれます。これは、従来のワイヤー矯正に比べて、顎関節にかかるストレスを軽減できる大きなメリットのひとつです。
また、取り外しが可能で清掃しやすいため、矯正中でも口腔内を清潔に保ちやすく、歯ぐきや周囲組織の健康を守る上でも理想的な環境が維持されます。
「見た目」だけでなく「機能」も重視した治療を選ぼう
現代の矯正治療は、美しさと健康のどちらかを選ぶものではありません。両立させる時代です。特にインビザラインのようなマウスピース型矯正では、見た目のコンプレックスを解消しながら、正しい噛み合わせを実現できる可能性が十分にあります。
そのためには、信頼できる歯科医院でしっかりと咬合や顎関節の状態を診てもらい、あなたに合った治療計画を立てることが何より重要です。歯並びとアゴの健康を同時に守る矯正治療は、人生の質(QOL)を大きく向上させてくれる選択肢となるでしょう。
まずはご相談ください!
神奈川県伊勢原市の
見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)
『 つじむら歯科医院 伊勢原 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士