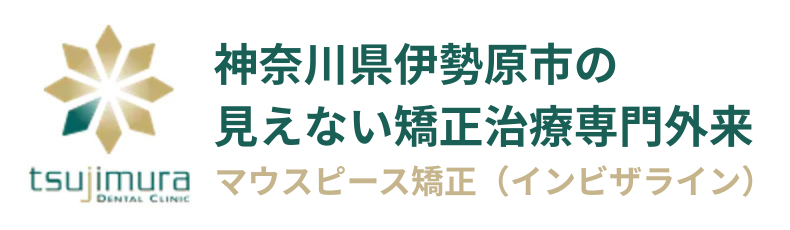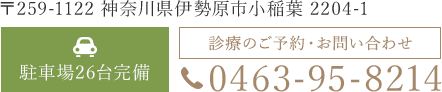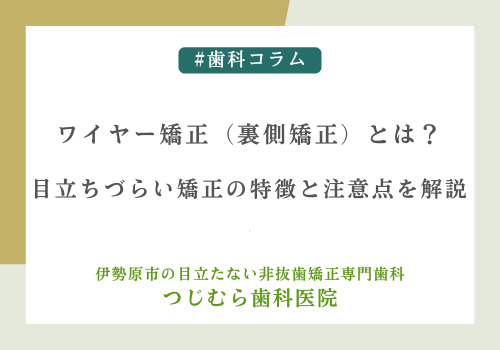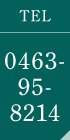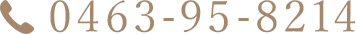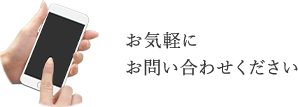矯正治療にはさまざまな方法がありますが、その中でも「装置が目立ちづらい矯正」として注目されているのがワイヤー矯正(裏側矯正)です。歯の裏側に装置をつけることで、会話や笑顔でも気づかれにくく、審美性を重視したい方に選ばれています。
本記事では、裏側矯正の特徴やメリット・デメリット、適応の目安やインビザラインとの違いまで詳しく解説します。
1.ワイヤー矯正(裏側矯正)とは?歯の裏に装置をつける目立ちにくい矯正法

ワイヤー矯正(裏側矯正)は、歯の裏側に装置を取り付けて歯並びを整える方法です。正面から見えにくいため、矯正治療をしていることに気づかれにくいのが特徴です。ここでは、その仕組みや装置の特徴、表側矯正との違い、そして普及の背景についてわかりやすく解説します。
裏側矯正の仕組みと装置の特徴
裏側矯正では、歯の裏側に小さな装置(ブラケット)を接着し、そこに細い金属の線(ワイヤー)を通して歯を少しずつ動かしていきます。仕組み自体は表側矯正と同じで、ワイヤーの力を利用して歯を計画的に移動させます。
ただし、装置を裏側に取り付けるため、歯の形に合わせたオーダーメイド設計となることが多いのが特徴です。近年はデジタルスキャナーや3D技術の導入により、より精密に設計できるようになり、治療の予測性が高まっています。また、装置自体の小型化が進み、以前より違和感や発音への影響が軽減されてきています。
表側矯正との大きな違い
表側矯正との違いで最も分かりやすいのは「見えにくさ」です。表側に装置をつける場合は会話や笑顔の際に金属が目立ちやすいのに対し、裏側矯正は装置が舌側にあるため正面からはほとんど見えません。そのため、人前に出る機会が多い方にとって安心感のある方法といえます。
また、歯の裏側は唾液が当たりやすく自浄作用(汚れを洗い流す作用)が働きやすい一方で、歯ブラシが届きにくく清掃が難しい場所でもあります。したがって、むし歯のリスクが低くなるとは一概にいえず、丁寧なセルフケアや定期的な歯科医院でのメンテナンスが不可欠です。
ワイヤー矯正(表側矯正)について詳しく知りたい方は、、こちらをご覧ください。
歴史と普及の背景
裏側矯正は比較的新しい治療と思われがちですが、実際には1980年代から研究・臨床応用が始まっています。当初は装置が大きく、違和感や発音への影響が大きいといった課題がありました。しかしその後の技術発展によりブラケットの小型化やデジタル設計が進み、治療の質が向上しました。
特に日本では「矯正治療をしていることを目立たせたくない」というニーズが強く、裏側矯正を導入する医院も増加。現在では、審美性を重視したい患者様の選択肢の一つとして広く取り入れられるようになっています。
2.ワイヤー矯正(裏側矯正)のメリット|正面から見えにくい安心感

矯正治療を検討する方にとって「装置が目立たないかどうか」は大きな関心ごとです。ワイヤー矯正(裏側矯正)は、歯の裏側に装置を装着するため、正面からは見えにくいのが特徴です。ここでは、裏側矯正が選ばれる主なメリットをわかりやすく紹介します。
見た目を気にせず矯正できる
裏側矯正の最も大きな特徴は、装置が正面からほとんど見えないことです。表側矯正では金属やセラミックの装置が前歯に装着されるため、会話や笑顔のときに目立ちやすくなります。一方で、裏側矯正は歯の裏側に装置をつけるため、矯正治療をしていることに気づかれにくいのが利点です。営業や接客など人と接する仕事をしている方や、就職活動や大切なイベントを控えている方にとって「見た目を気にせず過ごせる」ことは安心につながります。
幅広い歯並びに対応できる可能性
裏側矯正は、表側矯正と同じ仕組みを用いるため、さまざまな歯並びの改善に利用されます。歯が重なっているケース(叢生)や前歯が噛み合わない状態(開咬)など、複雑な歯列の改善にも適応できる場合があります。
マウスピース矯正のように「症例によっては対応が難しい方法」と比べると、裏側矯正は治療できる範囲が広いのが強みです。ただし、すべての症例に適しているわけではなく、状態によっては表側矯正や他の方法が勧められる場合もあります。
人前に出る機会が多い方に選ばれやすい
裏側矯正は「目立ちにくい」ことから、人前で話す機会が多い方に選ばれる傾向があります。営業や講師業の方、学生で面接を控えている方などがその例です。装置を気にせず自然に笑顔を見せられる点は、心理的な負担を和らげます。さらに、結婚式や成人式といった特別なイベントの時期に合わせて治療を始める方も少なくありません。矯正中であっても生活や対人関係に大きな支障が出にくいのは裏側矯正ならではのメリットです。
3.デメリットは?発音や舌の違和感・清掃のしにくさに注意

ワイヤー矯正(裏側矯正)は「目立ちにくい」という利点がありますが、その一方で治療を始める前に理解しておきたい注意点もあります。代表的なのは、舌に触れる違和感や発音への影響、そして清掃のしづらさによるむし歯リスクです。ここでは、裏側矯正ならではの課題について整理します。
舌に触れる違和感と慣れるまでの時間
裏側矯正は歯の裏側に装置(ブラケットやワイヤー)をつけるため、舌が常に金属に触れる状態になります。そのため、治療開始直後は「異物感がある」「舌が動かしにくい」と感じる方が多く、特に食事や会話の際に不便を覚えることがあります。
ただし、これは多くの場合一時的なもので、舌は環境に適応しやすいため数週間から数か月のうちに慣れていく方が多いとされています。慣れるまでの期間は個人差があり、早ければ数週間で違和感が減る場合もあれば、もう少し時間がかかることもあります。最初のうちはストレスを感じることもありますが、時間とともに生活に支障が少なくなるケースが大半です。
発音への影響
装置が舌に近いため、特定の発音がしにくくなる場合があります。特に「さ行」や「た行」、「ら行」など舌先を歯の裏に近づけて発音する音は影響を受けやすいとされています。治療を始めてすぐの時期には「滑舌が悪くなった」と感じることもありますが、舌が装置に慣れるにつれて改善することが多いです。
発音に不安を感じる方は、朗読や会話の練習を積極的に行うことで適応が早まることがあります。また、近年ではブラケット自体が小型化され、設計も改良されているため、以前に比べて発音への影響は軽減される傾向にあります。大切なのは、治療の開始時期を生活イベントに合わせて歯科医師と相談しておくことです。
清掃が難しくむし歯リスクが高まる可能性
歯の裏側は目で確認しにくい上に、ブラケットやワイヤーがあることで歯ブラシが届きにくくなります。そのため、食べかすやプラーク(歯垢)が残りやすく、むし歯や歯ぐきの炎症につながるリスクが高まることがあります。
このリスクを下げるためには、通常の歯ブラシだけでなく、先端が細いタフトブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどの補助清掃具を併用することが推奨されます。また、電動歯ブラシや口腔洗浄器を取り入れるのも有効です。さらに、歯科医院での定期的なクリーニングとチェックを受けることが、口腔内を健康に保つ上で欠かせません。患者さん自身の努力と専門家によるサポートを組み合わせることで、リスクを最小限に抑えることができます。
4.どんな人に向いている?ライフスタイルから見る適応
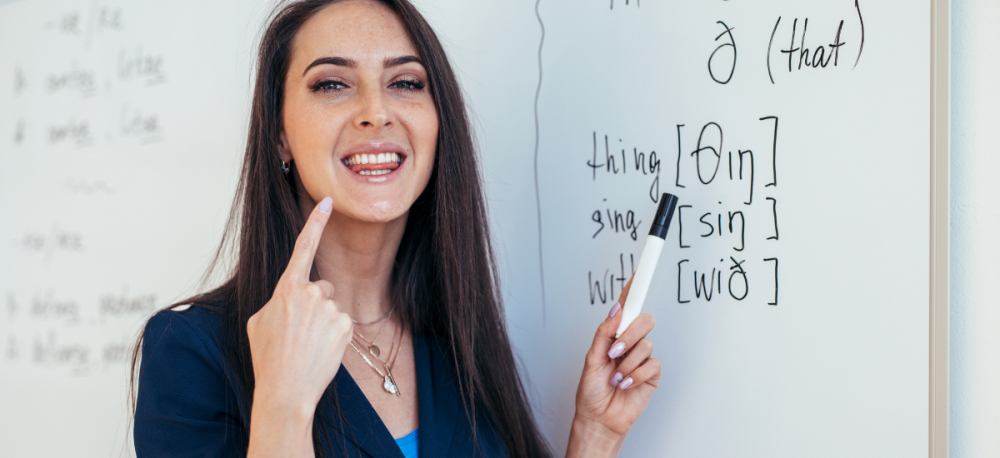
ワイヤー矯正(裏側矯正)は、装置が目立ちにくいというメリットがある一方、清掃や発音などに慣れる工夫が必要な治療法です。すべての方に一律で適しているわけではなく、生活習慣やセルフケアの姿勢によって向き・不向きがあります。ここでは、裏側矯正に向いていると考えられる方の特徴を整理します。
見た目を重視したい方
裏側矯正は「装置を目立たせたくない」と考える方に向いています。表側矯正では会話や笑顔のときに装置が見えやすくなりますが、裏側矯正は歯の裏側に装置をつけるため正面からはほとんど見えません。営業職や接客業などで人前に立つ機会が多い方や、就職活動や面接を控えた学生にとって安心感につながる方法といえます。
また、結婚式や成人式など人生の節目に合わせて治療を検討する方も多く、特に「人前で自然に笑顔を見せたい」というニーズに合致しやすい矯正法です。
丁寧なセルフケアができる方
裏側矯正は歯の裏側に装置がつくため、清掃が難しいという特徴があります。磨き残しが起こりやすく、むし歯や歯ぐきの炎症につながるリスクがあるため、普段以上に丁寧な歯磨きが必要です。毛先の細い歯ブラシやタフトブラシ、デンタルフロスなどを使って時間をかけてケアできる方に向いています。
また、定期的に歯科医院でのメンテナンスを受けられる方であれば、矯正中も口腔内を健康に保ちやすくなります。逆に、日常的なセルフケアを苦手とする方にとっては負担が大きく感じられる場合もあるため、自分の習慣を振り返ることが大切です。
矯正治療に前向きに取り組める方
裏側矯正は治療開始直後に舌の違和感や発音のしにくさを感じることがあります。これは多くの場合時間の経過とともに改善しますが、慣れるまでに一定の期間が必要です。そのため「少し違和感があっても前向きに治療を続けられる姿勢」がある方に向いています。
また、定期的な通院や歯科医師からの指示に従える方であれば、治療をスムーズに進めやすくなります。裏側矯正は「装置が見えにくい」という大きな利点がある一方で、快適さを得るには患者さん自身の協力も欠かせません。治療を積極的に受け止める姿勢が、裏側矯正を成功させる重要な要素です。
お口のお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
5.治療にかかる期間や費用の目安

矯正治療を検討する際、多くの方が気になるのが「どのくらいの期間が必要か」「費用はどれくらいかかるのか」という点です。ワイヤー矯正(裏側矯正)も例外ではなく、治療の内容や難易度によって大きく異なります。ここでは一般的な傾向を紹介し、理解の助けになる情報を整理します。
平均的な治療期間
裏側矯正の治療期間は、歯並びの状態や移動の量によって変わります。一般的には表側矯正と同じか、やや長めになる場合があります。これは装置が裏側にあるため調整が複雑になりやすいからです。
ただし近年は、ワイヤーやブラケットの設計が改良され、従来より効率的に歯を動かせるケースも増えています。早い方では2年程度で終了することもあれば、複雑な症例では3年以上かかることもあります。個人差が大きいため、治療期間は歯科医師の診断を受けて確認することが重要です。
費用の一般的な傾向
裏側矯正は、表側矯正やマウスピース矯正と比べて費用が高めになる傾向があります。理由は、装置が患者さんごとにオーダーメイドで作られることや、裏側に装置を取り付けるため高度な技術が必要だからです。
費用の目安は医院や地域によって大きく異なりますが、表側矯正より高額になることが多いとされています。部分的に裏側に装置をつける「部分矯正」を選ぶことで費用を抑えられる場合もあります。ただし、治療範囲や難易度によって総額は変動するため、必ず見積もりを確認する必要があります。
治療内容による変動要因
治療期間や費用は、歯並びの状態や治療計画によって左右されます。歯の移動が複雑で大きい場合は治療期間が延びやすく、それに伴い費用も高くなる傾向があります。逆に軽度の不正咬合であれば、比較的短期間で済む場合もあります。
また「全体矯正」か「部分矯正」かによっても大きく変わります。さらに、治療中にむし歯や歯周病の処置が必要になると、追加の通院や費用がかかることもあります。つまり裏側矯正は一律の料金体系ではなく、患者さん一人ひとりの口腔状態や治療内容によって大きな差が出るのです。
6.むし歯リスクやケアのポイント|裏側矯正ならではの注意点

ワイヤー矯正(裏側矯正)は、装置が目立ちにくいという大きなメリットがあります。しかしその一方で、歯の裏側に装置を取り付けることにより清掃が難しくなり、むし歯や歯ぐきのトラブルが起こりやすくなる可能性があります。ここでは、裏側矯正に伴うリスクと、それを防ぐためのケアのポイントを詳しく解説します。
装置周囲に汚れが残りやすい理由
裏側矯正は、歯の裏側にブラケット(小さな装置)やワイヤー(細い金属の線)を装着します。歯の裏側はもともと鏡で確認しにくい部分であり、加えて装置がつくことで歯ブラシの毛先が届きにくくなります。そのため、表側矯正と比べても磨き残しが生じやすいのが特徴です。
汚れが残るとプラーク(歯垢)が蓄積し、むし歯や歯周病のリスクが高まります。また、歯の裏側は舌に近いため食べ物のカスがたまりやすく、違和感や口臭の原因になることもあります。このため、裏側矯正中は普段以上に丁寧なセルフケアが求められます。
歯磨き・フロス・補助具を使った工夫
裏側矯正中は、通常の歯ブラシだけでは不十分なことが多いため、補助的なケア用品の活用が重要です。毛先が細いタフトブラシは、ブラケットの周囲や歯と歯の間など細かい部分に届きやすく有効です。また、デンタルフロスや歯間ブラシを使うことで、ワイヤーの間や歯の隙間にたまった汚れを落とすことができます。
さらに、矯正用に設計された電動歯ブラシや、ジェット水流で汚れを洗い流す口腔洗浄器を併用する方も増えています。これらのアイテムを適切に使うことで、セルフケアの精度を高め、むし歯や歯ぐきの炎症を予防しやすくなります。ただし、どの道具を使うかは口腔内の状態によって異なるため、歯科医師や歯科衛生士の指導を受けて選ぶと安心です。
定期検診と専門的なメンテナンスの重要性
自宅でのケアに加えて、歯科医院での定期的なメンテナンスは欠かせません。裏側矯正は構造的に磨き残しが起こりやすいため、セルフケアだけで完全に汚れを落とすのは難しいのが実情です。定期検診では、歯科衛生士による専門的なクリーニングで装置周囲のプラークや歯石を除去でき、むし歯や歯周病の早期発見にもつながります。
また、定期的にブラッシング方法のチェックや指導を受けることで、患者さん自身の清掃スキルも向上し、日常のケアがより効果的になります。裏側矯正を安全に進めるためには、患者さん自身の努力と専門家によるサポートを両立させることが重要です。
7.表側矯正との比較|裏側矯正だからできること

矯正治療といえば、歯の表側に装置をつける「表側矯正」が長年一般的でした。しかし近年は「目立たない矯正をしたい」というニーズの高まりにより、歯の裏側に装置をつける「裏側矯正」を希望する方も増えています。同じワイヤー矯正でありながら、装置の位置が違うだけで治療中の見え方や生活への影響に差が生じます。ここでは両者を比較しながら、裏側矯正の特性を整理します。
見た目における違い
表側矯正は歯の表側にブラケット(小さな装置)とワイヤーを取り付けるため、会話や笑顔の際に装置が目立ちやすい特徴があります。近年では白色やセラミック製の目立ちにくい装置も登場していますが、完全に見えなくすることはできません。そのため、矯正をしていることが周囲に伝わりやすい点は避けられません。
一方、裏側矯正は歯の裏側(舌側)に装置を取り付けるため、正面からはほとんど見えません。営業や接客など人と接する仕事をしている方や、結婚式や成人式といった特別なイベントを控えている方にとって「矯正をしていることを気づかれにくい」という点は大きな安心材料になります。治療中も自然な笑顔を見せやすいことは、裏側矯正ならではの強みといえるでしょう。
治療可能な範囲と効果の違い
表側矯正は長い歴史と実績を持ち、複雑な歯並びや大きな歯の移動など幅広い症例に対応できる方法です。治療の基本とされ、ほとんどの症例で選択されています。
裏側矯正も同じワイヤー矯正の仕組みを利用するため、基本的には表側矯正と同じように多くの症例に対応できます。ただし、装置が裏側にあることで歯の動かし方に制限が出る場合や、治療期間が表側よりやや長くなる場合もあります。近年では装置の小型化やワイヤー設計の改良によって効率的に歯を動かせるケースも増えており、以前と比べると差は縮まっています。
つまり「見た目に配慮しながらも、幅広い歯並びの改善を目指せる」という点が裏側矯正の特徴です。ただし、骨格的な要因や重度の不正咬合(かみ合わせの異常)では他の矯正方法の方が適している場合もあるため、歯科医師の診断を受けて選択することが大切です。
治療中の生活への影響
表側矯正は装置が目立ちやすいというデメリットがありますが、舌に触れることが少ないため、発音への影響や違和感が少なく慣れやすいのが利点です。また歯の表側は目で見て磨きやすいため、セルフケアの難易度も比較的低いといえます。
裏側矯正は「目立たない」という大きな利点がある反面、舌に装置が触れるため慣れるまでに違和感が出やすく、特定の音が発音しづらくなることがあります。また歯の裏側は歯ブラシが届きにくく、汚れが残りやすいため、タフトブラシやデンタルフロスなどを活用した丁寧なケアが欠かせません。
このように、表側矯正は「慣れやすさ」と「清掃のしやすさ」で優れ、裏側矯正は「目立ちにくさ」で優れています。どちらを選ぶかは、患者さん自身のライフスタイルや優先したいポイントによって変わります。
8.裏側矯正が難しい場合に検討できる選択肢
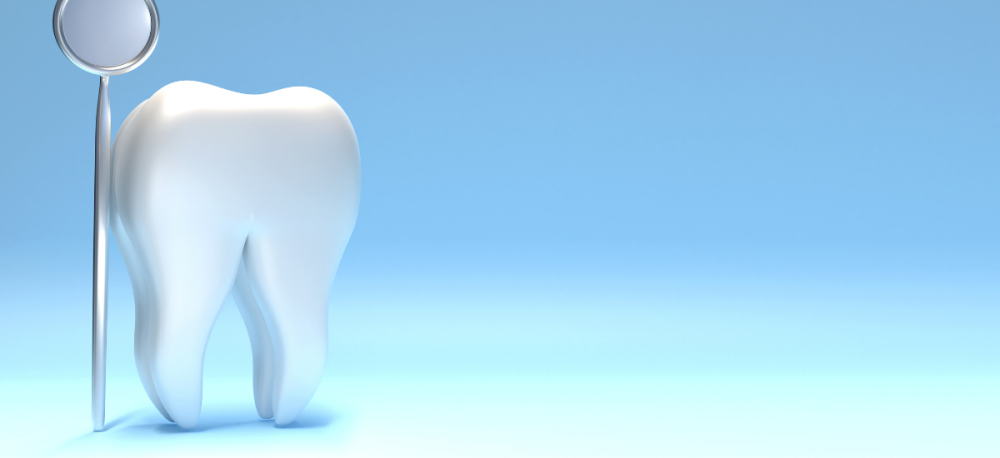
ワイヤー矯正(裏側矯正)は「目立ちにくさ」と「治療効果の高さ」を両立できる方法ですが、すべての症例に適しているわけではありません。歯並びやあごの形、生活習慣などによっては裏側矯正が難しい場合もあります。その際に考えられる代替方法について整理してみましょう。
裏側矯正の適応が難しいケース
裏側矯正は歯の裏側に装置を取り付けるため、歯の大きさや裏側のスペースが十分でないと装置を安定して設置できないことがあります。特に歯が小さい場合や、噛み合わせの状態によってはワイヤーが干渉してしまうケースがあります。また、装置が複雑になるため、清掃が難しくセルフケアに自信がない方はむし歯や歯ぐきのトラブルが起こりやすくなる可能性もあります。
これらの条件がある場合は、裏側矯正を無理に選ぶよりも、他の矯正方法を検討した方が安全で安心です。最終的な判断は歯科医師による診断で行われるため、適応かどうかを確認してから治療法を選択することが大切です。
表側矯正という選択肢
裏側矯正が難しい場合の基本的な代替方法は「表側矯正」です。表側矯正は歯の表面に装置をつけるため、装置の設置スペースに制約が少なく、ほとんどの症例に対応できるのが特徴です。矯正治療の中でも最も長い歴史と実績を持つ方法であり、多くのケースで安定した結果が得られています。
「装置が目立つのでは?」という不安もありますが、近年では白いブラケットや目立ちにくいワイヤーも開発されており、従来よりも審美性に配慮した治療が可能になっています。人前に出る仕事をしている方でも、表側矯正を選びながら自然な見た目を保つ工夫ができるようになっています。
マウスピース矯正(インビザライン)の可能性
「目立ちにくさを重視したいが、裏側矯正は難しい」と感じる方に適しているのが、マウスピース矯正(インビザライン)です。透明なマウスピースを使用するため装置がほとんど見えず、食事や歯磨きの際には取り外しが可能です。これにより口腔内を清潔に保ちやすく、日常生活への負担も軽減されます。
ただし、インビザラインには1日20時間以上の装着が必要という条件があり、自己管理が欠かせません。また、以前は複雑な症例には対応が難しいとされていましたが、近年はデジタル技術や補助的な装置を組み合わせることで適応範囲が広がりつつあります。それでも、重度の歯並びの乱れや外科的処置が必要な場合には他の方法が選ばれることもあるため、専門家による診断と相談が不可欠です。
さまざまな症例の矯正治療実績を掲載中です。
9.インビザラインとの違い|どちらが自分に合うのか?

ワイヤー矯正(裏側矯正)と同じく「目立ちにくい矯正法」として注目されているのが、透明なマウスピースを用いたインビザラインです。両者は見た目に配慮されている点では共通していますが、装置の仕組みや治療の進め方、生活への影響は異なります。ここでは、それぞれの特徴を比較し、自分に合った治療法を考えるヒントを紹介します。
装置の違いと生活への影響
裏側矯正は、歯の裏側にブラケット(小さな装置)とワイヤーを固定して取り付ける方法です。固定式のため、装置を外す必要がなく、常に歯に力をかけ続けられるのが特徴です。一方で、舌に装置が触れるため違和感を覚えたり、発音に影響が出ることがあります。慣れるまでに数週間から数か月かかることもあり、最初のうちは会話や食事に不便を感じることがあります。
インビザラインは、透明なマウスピース型の装置を一定期間ごとに交換して歯を動かします。最大の特徴は取り外しができる点で、食事や歯磨きの際に外せるため、口腔内を清潔に保ちやすく、生活上の制限が少ないのが利点です。ただし、1日20時間以上装着する必要があり、装着時間を守らなければ十分な効果が得られにくいという課題があります。つまり、裏側矯正は「自己管理の負担が少ない固定式」、インビザラインは「自己管理が重要な取り外し式」という違いが生活スタイルに直結します。
治療効果と適応範囲の違い
裏側矯正は、表側矯正と同じ仕組みを用いているため、複雑な歯並びや大きな歯の移動を伴う症例にも対応できることが多い方法です。叢生(歯が重なっている状態)や開咬(前歯が噛み合わない状態)、反対咬合(受け口)など、幅広い症例に用いられてきた実績があります。
一方、インビザラインは当初、軽度から中等度の症例を中心に用いられてきました。しかし、デジタル技術の進歩や補助装置との併用によって適応範囲が広がり、これまでより複雑な症例にも対応できるようになりつつあります。ただし、外科的な処置が必要なケースや重度の不正咬合では、依然としてワイヤー矯正が適していることも少なくありません。つまり、裏側矯正は「幅広い症例に対応しやすい方法」、インビザラインは「適応が広がってきたが自己管理が結果に影響する方法」と整理できます。
ライフスタイルに合わせた選び方
裏側矯正は、装置を外す必要がないため「装着を忘れる心配がない」点が強みです。見た目を気にせず、確実に歯を動かしたい方や、自己管理に自信がない方に向いている方法といえます。その一方で、舌の違和感や発音のしにくさ、清掃の難しさに慣れる工夫が必要です。
インビザラインは、取り外しができるため食事や歯磨きがしやすく、矯正中も快適に過ごしたい方に向いています。特に「人前で話す機会が多いが、発音への影響は避けたい」という方や、「衛生面を優先したい」という方に好まれます。ただし、装着時間を守る自己管理が欠かせず、習慣的に装置をつけ続けられる方でないと十分な効果を得ることが難しい場合もあります。
どちらを選ぶかは「歯並びの状態」と「生活習慣・性格」の両面を考慮することが大切です。自分のライフスタイルに合った治療法を選ぶことで、治療中の負担を少なくし、無理なく続けやすくなります。
インビザラインについて詳しく知りたい方は、、こちらをご覧ください。
10.目立ちにくい矯正を考えるなら、まずは専門家に相談を

ワイヤー矯正(裏側矯正)は、目立ちにくさと治療効果を両立できる選択肢の一つです。ただし、舌の違和感や清掃の難しさなど、生活に影響する注意点もあります。自分に合った矯正法を選ぶためには、裏側矯正だけでなく他の方法も知り、専門家と相談しながら検討することが重要です。
裏側矯正のメリットと注意点を理解する
裏側矯正は、会話や笑顔でも装置が目立ちにくい点が大きな魅力です。表側矯正と同じ仕組みを用いるため、幅広い症例に対応できる可能性があり、審美性と治療効果の両立を目指せます。
一方で、装置が舌に触れることで発音に影響が出やすかったり、歯磨きがしにくくむし歯リスクが高まりやすいといった注意点もあります。「見えにくい」だけを基準に選ぶのではなく、治療中の生活への影響も理解した上で判断することが大切です。
自分のライフスタイルに合うかを考える
矯正方法を選ぶ際には、歯並びの状態だけでなく「普段の生活習慣」との相性を考える必要があります。
裏側矯正は、固定式であるため装着を忘れる心配がなく、自己管理の負担が少ないのが利点です。見た目を気にせず、治療の確実性を重視したい方に適しています。
一方で、丁寧なセルフケアを継続できない方にとってはリスクが高まる可能性があるため、清掃習慣を見直す必要があります。また、発音や違和感に慣れるために多少の努力が必要になるため、「治療を前向きに受け止められる姿勢」があるかどうかも選択の基準になります。
複数の選択肢を比較して相談する
裏側矯正だけでなく、表側矯正やマウスピース矯正(インビザライン)など、目立ちにくさに配慮した方法はいくつもあります。
例えば、表側矯正は調整がしやすく幅広い症例に対応可能であり、目立ちにくい装置も開発されています。インビザラインは透明なマウスピースを使用し、食事や歯磨きの際に外せる点で快適ですが、装着時間の自己管理が必須です。
それぞれにメリットと注意点があるため、「どの治療法が自分に合うのか」は専門家の診断と相談を通じて検討することが欠かせません。矯正治療は長期間にわたるため、ライフスタイルや性格、清掃習慣を踏まえて選択することで、無理なく続けやすくなります。
あなたに合った矯正方法を一緒に考えましょう。お気軽に初診相談から!
神奈川県伊勢原市の
見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)
『 つじむら歯科医院 伊勢原 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士