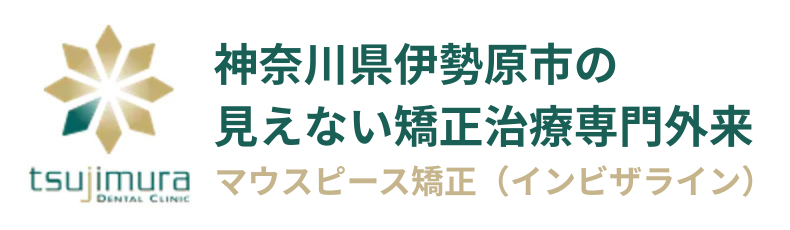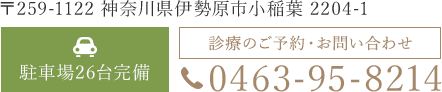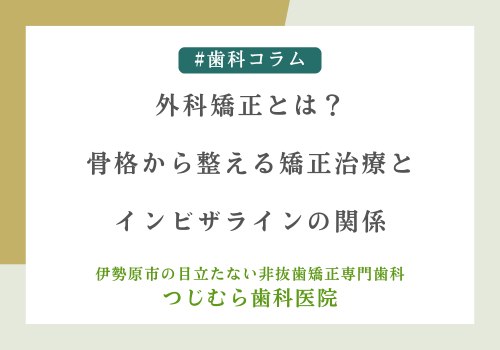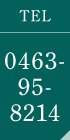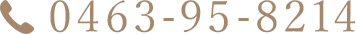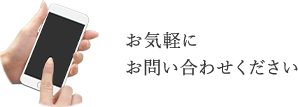1. 外科矯正とは?骨格から整える矯正治療の基本

歯並びを治す矯正治療にはさまざまな方法がありますが、すべてのケースが通常の矯正治療で解決できるわけではありません。
中には歯並びの乱れだけでなく、顎の骨格そのものに原因がある場合もあります。
そのようなときに検討されるのが「外科矯正」です。
外科矯正は、矯正治療と外科手術を組み合わせ、噛み合わせや見た目を骨格レベルから改善する治療法で、より根本的な解決をめざす点が大きな特徴です。
外科矯正の基本とは
外科矯正とは、歯の位置を動かすだけでは改善が難しい「骨格の不調和」に対して行われる治療です。
例えば、下顎が大きく前に出ている「受け口」や、逆に上顎が前に突き出している「出っ歯」などは、顎の骨の位置や大きさが原因で起こることが多く、通常の矯正だけでは根本的に治すことができません。
外科矯正では、まず矯正治療で歯の位置をある程度整え、次に外科手術によって顎の骨格を正しい位置に移動します。
その後、再度矯正治療を行い、噛み合わせや歯列の微調整を進めていきます。
複数のステップを踏むため治療期間は長期にわたりますが、見た目の改善と同時に噛む機能や発音のしやすさなど、日常生活に直結するメリットを得られるのが特徴です。
歯列矯正との違い
一般的な矯正治療は、ワイヤーやマウスピースを使い、歯に弱い力をかけて少しずつ移動させ、歯並びの乱れを改善する方法です。
多くの歯並びはこの方法で治療が可能ですが、顎の骨格に大きなズレがあると、歯だけを動かしても限界があります。
たとえば、下顎が過度に前に出ている場合、どんなに歯を並べ替えても上下の歯が正しく噛み合うことはありません。
このようなケースでは、骨格そのものを手術で修正しなければ、見た目も機能も根本的には改善できないのです。
外科矯正は、骨格を整えることで長期的に安定した噛み合わせを実現できるという点で、通常の矯正治療とは大きく異なります。
また、見た目の改善においても、歯列矯正だけでは難しい「顔全体のバランス改善」が期待できる点が特徴です。
顎の位置が整うことで横顔のラインが自然になり、口元の印象も大きく変わることがあります。
骨格を整える必要性
噛み合わせの不調和は、単に見た目の問題にとどまらず、健康にも深く関わります。
骨格にズレがあると上下の歯がしっかり噛み合わず、食べ物を細かく噛み切ることが難しくなる場合があります。
また、噛むときの力が一部の歯や顎関節に集中してしまい、顎関節症や歯の早期摩耗につながることもあります。
さらに、発音に支障をきたすケースもあり、日常生活において不便を感じることも少なくありません。
外科矯正によって骨格の位置を整えることで、こうした問題の改善が期待できます。
顎の関係が正しくなることで、噛む機能や発音が向上し、長期的な口腔の健康維持にもつながります。
見た目の美しさと同時に、機能面の改善をめざせるのが外科矯正の大きな価値といえるでしょう。
美しい横顔の条件について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
2. なぜ外科矯正が必要になるのか

歯並びの不正にはさまざまな種類がありますが、すべてが歯列矯正だけで解決できるわけではありません。
中には顎の骨格自体に大きなズレや不調和があり、歯だけを動かしても根本的な改善が難しいケースがあります。
こうした場合に選択肢となるのが外科矯正です。
外科矯正は、歯列矯正と外科手術を組み合わせて骨格から噛み合わせを整えることで、見た目だけでなく機能面の改善にもつながる治療法です。
歯並びだけで治せないケース
一般的な矯正治療は、歯の位置を動かすことで噛み合わせや見た目を改善します。
しかし、顎の骨格に大きなズレがある場合、歯を動かすだけでは理想的な位置に噛み合わせを合わせることができません。
例えば、下顎が極端に前に出ている「受け口」の場合、どれだけ歯を移動させても上下の前歯が自然に噛み合う位置には収まりません。
逆に、上顎が前に突き出している「出っ歯」のケースでも、歯列矯正だけでは対応が限界となります。
こうした骨格由来の不正咬合は、歯列矯正単独では改善が難しく、外科矯正によるアプローチが必要になります。
顎の成長と骨格の不調和
顎の骨格のズレは、多くの場合、成長期の顎の発育バランスが影響しています。
上顎と下顎の成長速度に差があると、顔全体のバランスが崩れ、噛み合わせにも不調和が生じます。
この骨格のずれが軽度であれば、通常の矯正治療で改善できることもありますが、成長が終了した成人では歯だけを動かす方法では限界があります。
外科矯正では、顎骨そのものを適切な位置へ移動するため、成長が終わった後でも根本的な改善が可能です。
これにより、噛み合わせや顔貌の調和を取り戻し、日常生活における不具合を解消することが期待できます。
健康・機能面に及ぶ影響
骨格のズレによる噛み合わせの不調和は、見た目だけでなく、健康や生活の質にも影響を及ぼします。
上下の歯がしっかりと噛み合わないと、食べ物をうまく噛み切れず、消化に負担をかけてしまうことがあります。
また、噛む力が一部の歯や顎関節に集中することで、歯の早期摩耗や顎関節症の原因になる場合もあります。
さらに、発音がしにくい、口元の筋肉に負担がかかるといった問題も起こり得ます。
こうした機能面でのトラブルは日常生活の不便さにつながるため、骨格を整える外科矯正によって改善が期待されるのです。
3. 外科矯正が適応となる症例

すべての不正咬合に外科矯正が必要なわけではありません。
多くの場合、歯列矯正だけで十分に改善が可能です。
しかし、顎の骨格に大きな不調和がある場合には、通常の矯正治療では根本的な解決が難しく、外科矯正が選択肢となります。
ここでは、どのような症例が外科矯正の適応となるのかを整理し、歯列矯正との違いを理解する手助けとなる情報を紹介します。
顎の位置に大きなズレがある場合
上下の顎の位置関係に大きな差があると、歯だけを動かしても噛み合わせが正しく整いません。
代表的なものが「下顎前突(受け口)」や「上顎前突(出っ歯)」です。
これらは顎骨の前後的な位置の不調和が原因となっており、歯を並べ直すだけでは解決できません。
また、上下の顎が横方向にずれている場合や、上下の歯の中心が大きくずれている場合も、外科的なアプローチが必要になることがあります。
このように、骨格レベルの問題が関与している場合は、外科矯正が検討されます。
骨格性不正咬合の具体例
外科矯正が適応となる骨格性不正咬合には、いくつかの代表的なタイプがあります。
・下顎前突(受け口):下顎が前に出ているため、上下の前歯が反対に噛み合う状態。
・上顎前突(出っ歯):上顎が過度に前方に突出している状態。
・開咬:奥歯は噛み合っているのに前歯が噛み合わず、前方に隙間がある状態。
・顔面非対称:片側の顎の成長が強く、顔が左右非対称になっている状態。
これらは歯の位置だけでなく顎骨の大きさや位置に起因しているため、歯列矯正だけでは根本的な改善が難しいのです。
外科矯正によって顎の骨を適切な位置に整えることで、噛み合わせと顔貌のバランスを取り戻すことができます。
顔のバランスに関わるケース
骨格の不調和は、噛み合わせだけでなく顔全体の印象にも影響します。
例えば、下顎が大きく前に出ていると、横顔のラインが崩れやすく、口元の印象も変化します。
また、顎が小さすぎる場合には、下顔面が後退して見えるなど、顔全体のバランスに影響することもあります。
このように、骨格の問題は「噛みにくい」「発音しにくい」といった機能的な不便さに加えて、「顔の見た目が気になる」といった審美的な悩みにもつながります。
外科矯正では顎の位置を根本から修正することで、噛み合わせの改善と同時に顔貌の調和もめざすことができます。
まずはつじむら歯科医院の症例をご覧ください
4. 外科矯正の治療の流れ

外科矯正は、通常の矯正治療に比べて治療プロセスが複雑です。
歯並びを整えるだけでなく、顎の骨格そのものを手術で移動させるため、検査から診断、矯正治療、外科手術、そして術後の調整まで、いくつものステップを経て進められます。
治療期間は数年にわたることもありますが、計画的に進めることで機能面と審美面の両立をめざすことができます。
ここでは外科矯正の一般的な流れを紹介します。
精密検査と診断
外科矯正を行う際は、まず歯や顎の状態を詳細に把握するための精密検査を行います。
レントゲン写真、CT撮影、歯型の採取、口腔内写真などを通じて、骨格や歯列の状態を総合的に確認します。
さらに、顎の動きや噛み合わせの力のかかり方も分析し、治療の必要性と最適な方法を判断します。
この段階で重要なのは、通常の矯正で対応できるのか、外科矯正が必要かを明確に見極めることです。
顎の骨格的なズレが大きい場合には、外科手術を組み合わせる治療計画が立てられます。
診断結果に基づき、治療全体の流れや期間、想定される手術内容が説明され、患者さんが理解したうえで治療がスタートします。
手術前の矯正治療
外科手術に進む前に、多くの場合「術前矯正」と呼ばれる治療が行われます。
これは、顎の手術をより正確に行うために歯列を整える準備段階です。
歯がデコボコに並んでいたり、噛み合わせが極端にずれていたりすると、手術によって顎を正しい位置に移動しても歯同士がうまく噛み合いません。
そのため、あらかじめ歯を適切な位置に並べ直す必要があります。
術前矯正は数か月~2年程度と幅があり、症例によって期間は異なります。
患者さんにとって根気のいる期間となりますが、この準備があることで手術後の安定性が高まります。
術前矯正を通じて、歯列が整い、顎の骨格が移動した際に理想的な噛み合わせになるようコントロールすることが可能になります。
手術・術後の矯正・安定化まで
術前矯正が完了すると、いよいよ顎の骨格を整える外科手術が行われます。
代表的な手術には、下顎の骨を後方に移動させる方法や、上顎を前方・後方に移動させる方法などがあり、症例に応じて適切な方法が選択されます。
手術は全身麻酔で行い、入院期間は術式や施設により数日~約1週間前後と異なります。
手術によって顎の骨格が整った後も、治療は終わりではありません。
手術直後は歯列と骨格がまだ完全には安定していないため、術後矯正を行って噛み合わせの微調整を続けます。
この術後矯正の期間は1年ほどかかることもあり、長期的に安定した状態をつくるために欠かせないプロセスです。
最終的に、噛み合わせと顔のバランスが整い、機能的にも審美的にも改善された状態が完成します。
その後も保定装置を使って後戻りを防ぎ、長期的に成果を維持していくことが大切です。
5. 外科矯正のメリットとリスク

外科矯正は、骨格から噛み合わせを整えることで根本的な改善をめざせる治療法です。
その効果は大きく、見た目や噛む力、発音の改善など、患者さんの生活の質に直結するメリットがあります。
しかし一方で、外科手術を伴うためリスクや注意点も存在します。
ここでは、外科矯正のメリットとリスクを整理し、治療を検討するうえでの理解を深めていきましょう。
顔貌や噛み合わせの大幅な改善
外科矯正の最大のメリットは、骨格に由来する不正咬合の原因にアプローチし、改善をめざす治療である点です。
歯列矯正だけでは整えられない顎の前後的なズレや左右のバランスを、手術によって修正することが可能になります。
見た目の面では、顎の突出や後退が解消されることで顔全体のバランスの改善が期待できる場合があります。
また、噛み合わせが正しくなることで、食べ物をしっかり噛み切れるようになり、咀嚼効率が改善します。
さらに、上下の歯が安定して噛み合うことで発音が改善する場合があり、日常生活の快適さの向上につながることがあります。
発音・咀嚼機能の向上
外科矯正によって顎の位置が適切に整うと、単なる見た目の改善にとどまらず、機能的な恩恵も得られます。
噛み合わせのバランスが取れることで食事中の負担が軽減され、消化にも良い影響を与えると考えられています。
また、歯と顎の関係が整うことで、発音しづらかった音が改善される場合もあります。
特にサ行やタ行の発音は歯と舌の位置関係が重要であり、骨格の不調和が解消されることで発音がクリアになるのです。
機能面の改善は、患者さんにとって生活の質を大きく高めるメリットといえるでしょう。
治療期間や手術リスクへの理解
一方で、外科矯正にはリスクや注意点も伴います。
まず、治療期間が長期にわたる点です。術前矯正、外科手術、術後矯正という流れを踏むため、数年単位での治療を想定する必要があります。
また、外科手術そのものには全身麻酔を用いるため、手術リスクがゼロではありません。
出血や腫れ、術後の痛みなど身体的な負担もあります。
さらに、入院や回復に一定の期間が必要になるため、日常生活への影響も考慮する必要があります。
外科矯正は高い効果が期待できる治療ですが、こうしたリスクを理解し、十分な説明を受けたうえで検討することが大切です。
メリットとリスクの両面を知ることで、自分にとって納得できる治療の選択につながります。
6. 外科矯正で用いられる矯正装置

外科矯正は、顎の骨格を整える外科手術と矯正治療を組み合わせて行います。
そのため、治療の各段階で使用される矯正装置の役割はとても重要です。
特に「術前矯正」と「術後矯正」では装置の違いが大きく、患者さんにとって治療中の快適さや見た目にも関わります。
ここでは、外科矯正で主に用いられる装置の特徴を整理し、ワイヤー矯正とマウスピース矯正(インビザライン)の違いを解説します。
ワイヤー矯正が主流である理由
外科矯正の治療では、術前矯正でワイヤーが選ばれることが多く、症例によりアライナーとの併用が行われることもあります。
理由のひとつは、ワイヤー矯正が「歯を三次元的に細かくコントロールできる」点にあります。
術前矯正では、顎の手術後に歯が理想的に噛み合うよう、歯列をあらかじめ整えておく必要があります。
その際、歯の移動量や方向を正確にコントロールできるワイヤー矯正は、治療計画通りに進めやすいのです。
また、外科手術の際には、上下の歯を正しい位置で噛み合わせるための「サージカルスプリント」と呼ばれる装置を併用しますが、これもワイヤー矯正との相性が良いため、現在も多くの症例で選ばれています。
マウスピース矯正との違い
近年、透明で目立ちにくいマウスピース矯正(インビザラインなど)も注目されていますが、外科矯正においては単独で用いられることは少ないのが現状です。
理由は、術前矯正において歯を大きく動かす必要がある場合、マウスピースではコントロールが難しいことがあるためです。
しかし、まったく使えないわけではありません。
症例によっては、術前矯正の一部や術後矯正の仕上げにマウスピースを活用することもあります。
特に術後は骨格が整っているため、見た目に配慮したい方や装置の取り外しができる快適さを重視する方にとって、マウスピース矯正は有効な選択肢となることがあります。
装置選択の重要性
外科矯正では、装置の選択が治療の進行や結果に直結します。
ワイヤー矯正は高いコントロール性から現在の主流であり、手術との連携面でもメリットが大きい方法です。
一方で、マウスピース矯正は見た目の自然さや清掃のしやすさといった利点があり、術後矯正での活用が広がっています。
装置の選択は一律ではなく、症例ごとの骨格の状態や歯列の難易度、患者さんの希望によって異なります。
治療の目的は長期的な安定を目標とします(術後の保定・メンテナンスが重要です)。
そのために最適な装置を選ぶことが大切です。
7. インビザラインと外科矯正の併用が注目される理由
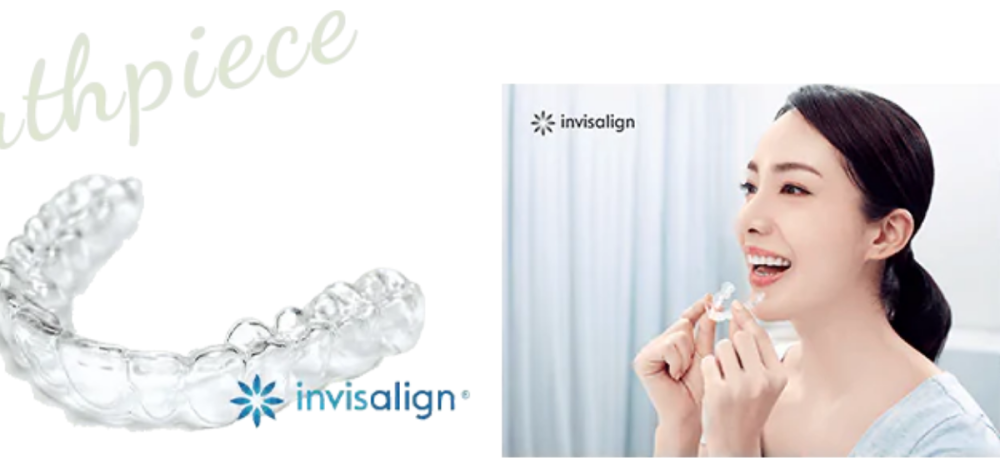
外科矯正は、顎の骨格にアプローチして根本的な改善をめざす治療ですが、近年では従来のワイヤー矯正だけでなく、マウスピース型矯正装置「インビザライン」を併用するケースが増えてきました。
インビザラインは透明で目立ちにくく、取り外しができるため、治療中の負担を軽減できる点が大きな特徴です。
外科矯正における補助的な役割としてインビザラインが注目されている理由を整理してみましょう。
術前・術後の歯列調整に活用できる
外科矯正では、手術前後に歯並びを調整する必要があります。
特に術後は、骨格が整った状態で噛み合わせを微調整する段階となります。
このとき、インビザラインを用いることで、目立たずに歯列を整えることが可能です。
インビザラインは透明なマウスピースを段階的に交換しながら歯を動かすため、見た目に配慮しながら治療を続けたい患者さんに適しています。
また、術前の一部の調整や術後の仕上げに取り入れることで、より快適な治療環境を提供できる点も大きな利点です。
治療中の見た目や快適さを保てる
外科矯正は長期的な治療となるため、治療中の見た目や生活の快適さも大切な要素です。
従来のワイヤー矯正は装置が目立ちやすく、食事や歯磨きの際に不便を感じることがありました。
一方、インビザラインは透明で周囲に気づかれにくいため、治療中の心理的負担を軽減できます。
さらに、取り外しが可能なため、食事の際に制限が少なく、装置の清掃もしやすいというメリットがあります。
長期間にわたる外科矯正の過程で、日常生活の質をできるだけ維持できる点は、インビザラインを併用する大きな魅力といえるでしょう。
清潔さと衛生管理を保ちやすい
矯正治療中は、装置の周囲に食べかすや歯垢がたまりやすく、むし歯や歯周病のリスクが高まります。
特に外科矯正では治療期間が長くなるため、口腔内を清潔に保つ工夫が欠かせません。
インビザラインは取り外して歯磨きやフロスができるため、口腔内の衛生管理がしやすいという大きな利点があります。
また、術後の回復期には歯ぐきや口腔内がデリケートな状態になりやすいですが、インビザラインであれば柔らかい素材で作られているため、口腔内への負担を最小限に抑えられる点も安心材料となります。
インビザラインについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
8. 術後の安定とインビザラインの役割


外科矯正は、顎の骨格を手術で整えることで大きな改善をめざす治療法です。
しかし、手術を終えた直後は、骨格と歯列がまだ完全に安定していません。
そのため、術後に適切な矯正治療を行い、噛み合わせを微調整しながら長期的な安定を図ることが重要です。
ここで役立つのがマウスピース型矯正装置「インビザライン」です。
術後の安定をサポートする役割を持ち、快適さや衛生面でも多くの利点があります。
術後矯正の重要性
外科手術によって顎の骨格を理想的な位置に移動させても、それだけで治療が完了するわけではありません。
顎の位置が変化すると、歯列と噛み合わせが新しい骨格に適応するまでに時間がかかります。
そのため、術後に「術後矯正」と呼ばれる歯列の微調整が必要となります。
術後矯正の目的は、噛み合わせを安定させ、長期的に正しい機能を維持することです。
これを怠ると、再び歯並びや噛み合わせに不調和が生じ、治療の成果が十分に発揮されない可能性があります。
そのため、術後矯正は外科矯正全体の成功を左右する重要なプロセスなのです。
インビザラインで行う微調整
従来は術後矯正でもワイヤー矯正が用いられることが一般的でしたが、近年ではインビザラインが術後の補助的な役割として注目されています。
インビザラインは透明なマウスピースを段階的に交換しながら歯を動かすため、見た目を気にせずに治療を続けられる点が大きな利点です。
術後は、噛み合わせの細かい調整や歯の位置の微修正が必要になる場合があります。
インビザラインはデジタルシミュレーションを用いて治療計画を立てるため、歯の移動を予測しやすく、仕上げの段階で効果的に活用できます。
また、装置が取り外し可能であるため、術後の敏感な口腔内にも優しく、清潔に保ちやすいのも魅力です。
長期的な安定と健康維持への効果
術後の安定を守るためには、歯列を正しい位置に保ち、後戻りを防ぐことが欠かせません。
治療後は専用の保定装置(マウスピース型のリテーナー等)を用いて後戻りを抑えます。
また、取り外して歯磨きや食事ができるため、むし歯や歯周病のリスクを抑えながら口腔内を健康に保てます。
外科矯正は長期間にわたる治療だからこそ、日常生活での快適さや衛生面の維持が重要です。
その点でインビザラインは、術後矯正をサポートするだけでなく、治療成果を長期的に安定させるための有効なツールといえるでしょう。
9. 外科矯正を考えるときに知っておきたい視点
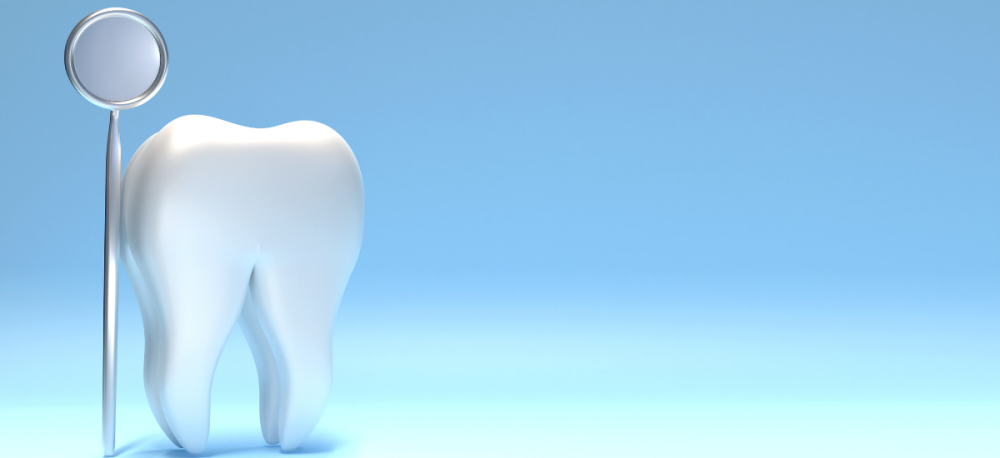
外科矯正は、通常の矯正治療に比べて治療規模が大きく、治療期間や身体への負担も少なくありません。
そのため、実際に検討する際には「自分にとって必要なのか」「どのような流れで進むのか」といった点を冷静に理解することが大切です。
外科矯正は骨格から整える根本的な治療ですが、決して誰にでも必要なわけではありません。
ここでは治療を考える際に持っておきたい視点を整理します。
専門的な診断の重要性
外科矯正が必要かどうかを判断するのは、専門的な診断に基づきます。
見た目だけで「顎が出ているから手術が必要」と考えるのは早計であり、実際には歯列矯正だけで改善できるケースも少なくありません。
精密検査ではレントゲンやCT、歯型の採取などを行い、顎骨の位置や成長のバランス、歯のかみ合わせを総合的に分析します。
そのうえで、通常の矯正で対応できるのか、外科矯正を併用すべきかが明らかになります。
こうした診断の過程を経ることで、自分に必要な治療の方向性が見えてきます。
治療期間と生活への影響を理解する
外科矯正は、術前矯正、外科手術、術後矯正という流れを踏むため、治療期間が長くなる傾向にあります。
全体で数年に及ぶケースもあり、学業や仕事、日常生活に影響が出る場面も考えられます。
また、手術後は数日の入院や一定期間の回復が必要となり、その間は食事や会話に制限が出ることもあります。
こうした治療のプロセスを理解し、あらかじめスケジュールを見通しておくことで、不安を軽減しながら治療に臨むことができます。
治療効果だけでなく、日常生活との両立を考える視点を持つことが大切です。
自分に合った治療方法を選ぶ視点
外科矯正は大きな効果が期待できる一方で、必ずしも全員が対象になるわけではありません。
骨格の不調和が軽度であれば、通常の矯正治療で十分改善できることもあります。
また、近年ではインビザラインをはじめとするマウスピース矯正の技術も進歩しており、症例によっては外科矯正を併用せずに対応できる場合もあります。
重要なのは「自分の症状にどの治療が適しているのか」を理解することです。
そのためには、治療法を一つに決めつけるのではなく、複数の選択肢を知り、それぞれのメリット・注意点を比較する姿勢が欠かせません。
外科矯正を検討する際も、視野を広く持ちながら治療を理解することが、自分に合った方法を選ぶ第一歩となります。
10. 外科矯正を理解し、インビザラインという選択肢も知ろう

外科矯正は、顎の骨格から噛み合わせを整えることで、見た目と機能の両方を改善できる根本的な治療法です。
しかし、手術を伴うため治療の流れは複雑で、期間も長くなります。
だからこそ「自分には外科矯正が必要なのか」「どのような装置を使うのか」を理解し、納得のうえで選択することが大切です。
そして近年では、ワイヤー矯正だけでなく、インビザラインを併用することで治療の幅が広がっています。
外科矯正の役割を正しく理解する
外科矯正は、通常の矯正では対応できない骨格のズレに対して行う治療です。
顎の前後的な位置や左右のバランスを外科手術で整え、そのうえで歯並びを仕上げるため、根本から噛み合わせを改善できるのが大きな特徴です。
これにより、咀嚼や発音といった日常生活での機能が向上するだけでなく、顔全体の調和が整い、見た目の改善にもつながります。
ただし、外科矯正は誰にでも必要な治療ではありません。
精密検査と専門的な診断を受け、自分の症例に本当に必要かどうかを正しく理解することが大切です。
インビザラインによって広がる可能性
従来、外科矯正はワイヤー矯正と組み合わせるのが一般的でした。
しかし、近年では透明で取り外し可能なマウスピース矯正「インビザライン」を併用するケースも増えています。
術前の歯列調整や術後の噛み合わせの微調整にインビザラインを活用することで、治療中も目立ちにくく、衛生的に過ごすことができます。
特に術後の安定化や仕上げの段階では、インビザラインの快適さと清掃のしやすさが大きな利点となります。
患者さんにとって治療の心理的負担を軽減し、長期的に安定した成果を維持するサポートとして役立つのです。
当院の方針とご案内
当院は外科手術は実施しておりません。健康な歯の抜歯も原則行いません(※親知らずを除く)。マウスピース型矯正装置(インビザライン)による非外科・非抜歯の矯正を専門に行っています。記事でご紹介したように、外科矯正が有効となるケースもありますが、まずは精密検査・診断により非外科で改善が見込めるかを丁寧に評価いたします。
もし非外科での対応が難しいと判断される場合には、連携医療機関での治療も含めて、中立的に選択肢をご案内します。外科矯正について説明を受けた方や手術を勧められた方も、一度ご相談ください。非外科・非抜歯でどこまで目指せるか、一緒に確認していきましょう。
※治療の効果・期間・費用には個人差があります。詳細は精密検査後にご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください
神奈川県伊勢原市の
見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)
『 つじむら歯科医院 伊勢原 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士