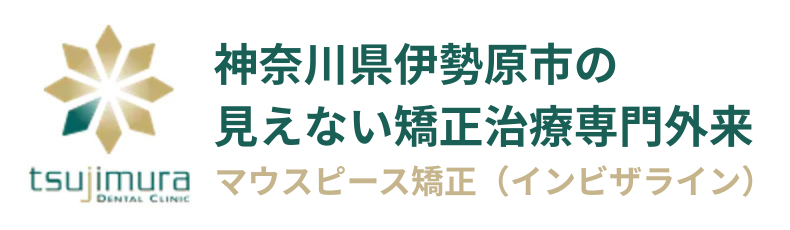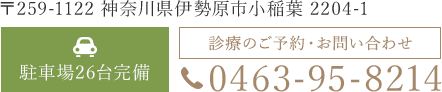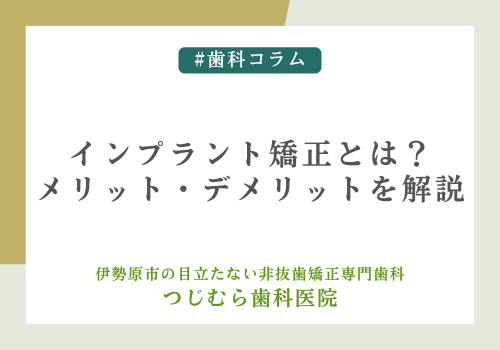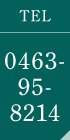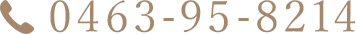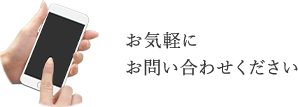矯正治療をより精密に、そして効率的に行うために開発された「インプラント矯正」。
近年では、難しい歯の動きにも対応できる新しい治療法として注目されています。
小さなネジ(アンカースクリュー)を一時的に支えとして用いることで、歯を狙った方向へ正確に動かすことができるのが特徴です。
一方で、外科的な処置を伴うため、すべての方に適しているわけではありません。
本記事では、インプラント矯正の仕組みやメリット・デメリット、治療の流れなどをわかりやすく解説します。
1.インプラント矯正とは?

近年、「インプラント矯正」という言葉を耳にする方が増えています。
これは、歯を動かすための支えとして小さなネジを骨に固定する矯正法で、従来よりも正確かつ効率的に歯を移動できるのが特徴です。
一般的なワイヤー矯正だけでは難しかった動きが可能になり、治療期間の短縮にもつながることがあります。
ここでは、インプラント矯正の仕組みや対象となる症例、処置の流れについてわかりやすく解説します。
矯正用インプラントの仕組みとは?
「インプラント矯正」とは、歯を失った際に人工歯根を埋め込む「インプラント治療」とはまったく異なる矯正方法です。
ここで用いられるのは、矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)と呼ばれる、直径1〜2mm・長さ6〜10mmほどの非常に小さなチタン製のネジです。
これを歯を支えるあごの骨(歯槽骨)に一時的に埋め込み、歯を動かす際の固定源(アンカー)として利用します。
通常の矯正では、歯を動かすときに他の歯を支点として引っ張り合うため、支点側の歯まで動いてしまうことがありました。
しかし、スクリューを動かない支点として使うことで、不要な歯の移動を防ぎ、目的の歯だけを狙って動かせるようになります。
これにより、より正確で計画的な歯の移動が可能となり、矯正治療全体の質を高めることができます。
どんな症例に使われるのか
インプラント矯正は、すべての患者様に必要な治療ではありませんが、特定の症例で有効とされます。
たとえば、奥歯をうしろ側へ動かす(後方移動)ケースや、抜歯後のスペースを効率よく閉じたい場合などです。
また、噛み合わせのズレが大きい場合や、歯列全体をしっかり整えたいケースにも活用されます。
通常の矯正では、歯を支点にすると他の歯まで動くことがありますが、スクリューを固定源とすることで支点が動かず、狙った歯だけを効率的に動かすことが可能です。
ただし、すべての方が適応となるわけではありません。
以下のような条件がある場合は、慎重な検討や前処置が必要です。
・成長期(顎の骨が発達途中)のお子様:骨がまだ安定していないため、スクリュー位置が変化するおそれがあります。
・骨の厚みや硬さが不十分な方:スクリューが安定しづらい場合があります。
・歯周病・糖尿病など、骨の健康に影響を与える疾患をお持ちの方:炎症や治癒遅延のリスクが上がることがあります。
・骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート製剤・デノスマブ等)を使用中の方、抗凝固療法中の方:顎骨への影響や出血傾向を考慮し、内科主治医との連携が必要になる場合があります。
・喫煙習慣のある方や清掃が不十分な方:傷の治りが遅く、感染のリスクが高まる傾向があります。
これらの要因がある場合でも、口腔環境を整えることで安全に治療できるケースもあります。
事前の精密検査(CT・レントゲン)で骨の状態を確認し、全身の健康を踏まえた上で治療計画を立てます。
患者様一人ひとりの状態を評価し、無理のない範囲で治療を進めることが重要です。
処置の流れと痛みの少なさ
インプラント矯正のスクリュー埋入は、局所麻酔のもとで行う比較的シンプルな処置です。
多くの場合は10〜15分程度で終了しますが、埋入する部位や本数、骨の状態によって所要時間は前後します。
処置後は痛みや腫れに個人差があるため、医師の指示に従い当日は安静を心がけ、1〜2日は硬い食品や刺激物を控えるなどの配慮をお願いします。
必要に応じて鎮痛薬や洗口液を処方します。
スクリューは矯正装置(ワイヤーやゴムなど)と連結し、歯に計画した方向の力をかけて少しずつ移動させます。
通院は数週間〜数か月おきに行い、装置の調整や清掃状態、スクリューの安定性を確認します。
当日も会話ややわらかい食事は可能な場合が多いですが、数日は硬い食品を避け、患部を刺激しないようにしてください。
治療が終了したら、スクリューは短時間で取り外します。
除去時の痛みは軽度で済むことが多いものの、一時的な違和感や軽い出血がみられる場合があります。
傷口は通常数日で自然に治癒しますが、異常があれば早めにご連絡ください。
装置は小型で目立ちづらい設計ですが、装着部位によっては見える場合もあります。
清掃は通常の歯みがきにタフトブラシや歯間ブラシを併用すると効果的です。
まれに炎症やスクリューの緩み・脱落、感染などの合併症が生じることがあるため、指示どおりのセルフケアと定期受診が重要です。
つじむら歯科医院では、非抜歯・非外科を基本とした矯正方針のもと、インプラント矯正(矯正用アンカースクリュー/TAD)は必要と判断される症例に限って補助的に併用します。適応可否はレントゲンやCT等で骨の状態を確認し、個々の状況に応じて慎重に評価します。
本記事は一般的な医療情報の提供を目的としており、特定の治療を一律に推奨するものではありません。
より詳しい治療内容や設備については、つじむら歯科医院の「インプラント矯正」ページをご参照ください。
2.インプラント矯正が選ばれる理由

矯正治療にはさまざまな方法がありますが、「インプラント矯正」はその中でも特に精度と効率の高さが評価されています。
小さなスクリューを固定源にすることで、歯を計画的に動かせる点が従来の矯正との大きな違いです。
歯科医師にとっては治療設計の自由度が高く、患者様にとっては理想的な歯並びを短期間で実現できる可能性があります。
ここでは、多くの方がインプラント矯正を選ぶ理由を3つの視点から解説します。
正確な歯の移動を実現できる
従来の矯正治療では、歯を動かす際に別の歯を支点として利用するため、引っ張り合う力のバランスをとる必要がありました。
この仕組みでは、意図していない歯まで動いてしまう「意図しない歯の動き」が起きることもあります。
一方、インプラント矯正では歯を支えるあごの骨(歯槽骨)に直接、矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)を固定するため、支点が動くことはありません。
動かしたい歯だけを的確にコントロールでき、治療の精度を高めやすいのが特徴です。
たとえば、前歯を下げたい場合や奥歯をうしろ側へ動かす(後方移動)ケースでも、他の歯を動かさずに力を加えられます。
これにより、全体の噛み合わせを崩さずに整えることができ、治療後の安定性にも寄与します。
治療期間の短縮につながるケースがある
矯正治療は「長くかかる」と思われがちですが、インプラント矯正を併用することで、症例により短縮が期待できる場合がある
従来は、力のかけ方に制限があったため、歯を少しずつしか動かせませんでした。
しかし、動かない支点(アンカースクリュー)を利用することで、より効率的に目的の方向へ力を加えられます。
その結果、歯の移動スピードが上がり、症例によっては治療期間の短縮が期待できるようになりました。
また、歯を支える骨への負担が分散されるため、全体的にバランスよく動かすことができ、無理のない矯正計画を立てやすいのも特徴です。
ただし、治療期間には個人差があり、骨の状態や移動量によって異なるため、歯科医師の診断を踏まえて判断することが大切です。
見た目に影響しにくく、快適に過ごせる
「矯正装置が目立つのが気になる」「仕事中や人前で話すときに恥ずかしい」といった悩みを持つ方にも、インプラント矯正は適しています。
スクリューは非常に小さく、歯ぐきの上にわずかに金属の頭が出る程度で、会話中に他人から見えることはほとんどありません。
また、取り付け直後でも痛みや違和感は軽度であることが多く、日常生活への影響は最小限に抑えられます。
食事や発音への影響も少なく、装置の清掃は通常のブラッシングに加えてタフトブラシや歯間ブラシを併用することで十分に対応できます。
さらに、スクリューは治療終了後に短時間で取り外せるため、跡が残る心配もほとんどありません。
このように、見た目・快適さ・治療効果の3点を両立できる点が、多くの患者様に選ばれている理由といえます。
3.インプラント矯正の流れ

「インプラント矯正」と聞くと、手術のような大掛かりな治療をイメージする方もいますが、実際はとてもシンプルな流れで進みます。
スクリューの埋入も短時間で終わり、痛みや腫れもほとんどありません。
ここでは、カウンセリングから矯正終了までの基本的な流れを3つのステップに分けて、わかりやすくご紹介します。
治療を検討している方が、安心して一歩を踏み出せるように解説します。
ステップ1:診断と治療計画の立案
まず行うのは、精密な検査と治療計画の作成です。
インプラント矯正では、歯や骨の状態を正確に把握することが非常に重要です。
歯科医院ではレントゲンやCT撮影、口腔内スキャンなどを行い、スクリューをどこに埋め込むかを慎重に検討します。
歯を支えるあごの骨(歯槽骨)の厚みや角度、歯の根の位置を確認しながら、最も安全で効果的な場所を決めていきます。
同時に、全体の歯の動きをシミュレーションし、矯正のゴールを具体的に共有することで、患者様も治療の流れをイメージしやすくなります。
この段階で歯ぐきや骨の健康状態が良好であることが確認できれば、次のステップに進みます。
ステップ2:スクリュー埋入と矯正装置の装着
治療計画が決まったら、いよいよスクリューの埋入を行います。
処置は局所麻酔下で行い、歯ぐきに小さな穴を開けて矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)をねじ込むだけの短時間の手技です。
直径1〜2mmほどのチタン製スクリューを使用するため、痛みは軽度で済むことが多く、出血もごくわずかです。
処置時間は10〜15分ほどで完了し、その日のうちに食事や会話も可能です。
スクリューは骨にしっかり固定されているため支点が動かず、矯正装置(ワイヤーやゴムなど)を用いて歯を正確に移動させることができます。
見た目もほとんど目立たず、鏡を見ても小さな金属が少し見える程度です。
埋入後は軽い違和感を感じる場合がありますが、多くは数日で自然に慣れていきます。
ステップ3:歯の移動とスクリュー除去
スクリューを設置した後は、矯正装置を使って少しずつ歯を動かしていきます。
1〜2か月に1回程度のペースで通院し、歯の動きを確認しながらワイヤーやゴムの調整を行います。
スクリューは安定した固定源として機能し続けるため、歯が理想の位置に近づくまでしっかりサポートしてくれます。
動かしたい歯が目標の位置に達したら、スクリューを取り外す処置を行います。
除去は埋入よりも短時間で終わり、痛みもほとんどありません。
傷口は数日で自然に治癒し、跡が残ることはほとんどないため、安心して日常生活に戻れます。
その後は、歯並びが戻らないように固定して慣らす安定期間(保定)を設け、矯正治療は完了となります。
このようにインプラント矯正は、短時間・低負担・高精度の三拍子がそろった選択肢の一つとして検討されています。
4.インプラント矯正のメリット:精密で効率的な治療

「より短期間で理想的な歯並びにしたい」「できるだけ負担を減らしたい」と考える患者様にとって、インプラント矯正は選択肢のひとつとなる治療法です。
従来の矯正と比べ、支点が安定しやすいことから歯の動きを計画的にコントロールしやすく、症例によっては治療の効率化が期待できます。
ここでは、インプラント矯正の主なメリットを3つの観点からご紹介します。
① 動かしたい歯をピンポイントで動かせる
インプラント矯正の特徴は、支点の安定性が高いことです。
従来の矯正では、歯を動かす際に他の歯を支えとして利用するため、引っ張り合う力が生じ、思わぬ方向へ歯が移動してしまうことがありました。
インプラント矯正では、歯を支えるあごの骨(歯槽骨)に固定した矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)を支点として使うことで、力の方向を精密に設計しやすく、計画どおりの歯の移動に寄与します。
ただし、歯や骨の状態によってはスクリューの安定度が異なるため、治療効果や進行速度には個人差があります。
矯正医がCT画像などを用いて力の方向を慎重にシミュレーションし、無理のない範囲で歯を動かすことが大切です。
② 治療期間の短縮が期待できるケースもある
矯正治療はどうしても時間がかかる印象がありますが、インプラント矯正を併用することで治療期間の短縮が期待できる症例もあります。
支点が動かないため、歯を効率的に目的方向へ移動させやすいことが理由のひとつです。
その結果、従来よりも調整回数を減らせる場合や、奥歯をうしろ側へ動かす(後方移動)がスムーズになるケースも見られます。
とはいえ、治療期間は骨の状態や歯の動きやすさ、目標とする歯列の範囲などによって変動します。
早さだけを重視するのではなく、歯や骨に負担をかけすぎない適切なスピードで進めることが重要です。
担当医と相談しながら、自分に合ったペースを見極めましょう。
③ 見た目に目立ちづらく、快適に治療を続けられる
インプラント矯正に使われるスクリューは、直径1〜2mm程度の小さな金属製の器具です。
歯ぐきに埋め込むため外からはほとんど見えませんが、装着部位によってはわずかに見えることもあります。
装置は小型で、食事や会話への影響を最小限に抑えられることが多い一方で、装着直後に軽い違和感や発音のしづらさを感じる方もいます。
多くの場合は数日で慣れ、日常生活への支障はほとんどありません。
また、清掃も通常のブラッシングにタフトブラシや歯間ブラシなどを併用すれば十分対応できます。
痛みや不快感が続く場合は、早めに歯科医院でチェックを受けましょう。
適切なメンテナンスを続けることで、快適に治療を進められます。
5.インプラント矯正のデメリット・注意点を知っておこう

インプラント矯正は効果的な治療法ですが、外科的処置を伴うため注意が必要な点もあります。
ここでは、代表的な3つの留意事項をわかりやすくご紹介します。
① 外科的処置が必要になる
インプラント矯正で行うスクリュー埋入は、局所麻酔のもとで行う小規模な外科処置です。
処置時間は一般的に10〜15分程度と短く、多くの場合は日常生活への影響が少ない治療ですが、術後に軽度の腫れや違和感、出血を伴うことがあります。
歯を支えるあごの骨(歯槽骨)にスクリューを固定するため、口腔内を清潔に保つことがとても重要です。
清掃が不十分な状態が続くと、スクリュー周囲に炎症が起こり、まれに一時的な脱落が見られることもあります。
その場合は炎症が治まってから再埋入を検討します。
感染を防ぐためには、丁寧な歯みがき・洗口・定期的な通院が欠かせません。
また、痛みが長引く・強い腫れがある場合は、早めの受診が安心です。
② 適応できない・慎重な検討が必要なケース
インプラント矯正は多くの症例に対応できますが、すべての方に適しているわけではありません。
骨の量や密度、全身の健康状態によっては、スクリューが安定しづらく治療効果が得られにくいことがあります。
特に、以下のような方は慎重な検討が必要です。
・成長期の方(顎の骨が発達途中で、位置がずれるおそれがあります)
・骨の厚み・硬さが不十分な方(スクリューがしっかり固定されにくい場合があります)
・歯周病や糖尿病など、炎症や治癒に影響する疾患をお持ちの方
・骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート製剤・デノスマブ等)を服用中の方
・抗凝固療法中の方(出血や治癒遅延のリスクがあります)
・喫煙習慣のある方(血流が悪くなり、治癒が遅れる傾向があります)
これらのケースでは、事前に全身状態を詳しく確認し、必要に応じて内科主治医と連携して進めます。
また、歯周病の治療や生活習慣の改善を行うことで、安全に矯正が可能になるケースもあります。
③ スクリューの維持とメンテナンス
スクリューは、適切なケアを行えば安定して機能する装置です。
しかし、清掃不足や強い咬合圧、歯ぎしりなどの影響で緩みや脱落が起こる場合もあります。
日常のケアでは、歯科医師の指導に従い、タフトブラシや歯間ブラシなどを併用して清掃を行いましょう。
また、スクリュー周囲の違和感や装置の揺れを感じた場合は、早めに受診することが大切です。
治療終了後にはスクリューを取り外しますが、除去時の痛みは軽度であることが多く、傷口は数日で自然に治癒します。
ただし、糖尿病や喫煙、服薬などの影響で治りが遅れる場合もあるため、異常を感じた際は放置せず歯科医院に相談してください。
6.インプラント矯正が向いている人・向いていない人

インプラント矯正は、精度の高い歯の移動を実現できる優れた治療法ですが、すべての方に適応するわけではありません。
骨の状態や年齢、生活習慣などによって、治療の向き・不向きが分かれます。
ここでは、どんな方にインプラント矯正が向いているのか、また控えたほうがよいケースについて詳しく解説します。
治療を始める前に、自分の状態を客観的に知ることが大切です。
インプラント矯正が向いている人
インプラント矯正が特に効果を発揮するのは、歯の動きに制限がある症例や、治療を効率的に進めたい方です。
たとえば、奥歯をうしろ側へ動かす(後方移動)場合や、抜歯後のスペースを閉じたい場合など、従来の矯正では支点となる歯が動いてしまい、思うような結果が得られにくいことがありました。
そのようなケースで、矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)を固定源として利用することで、動かしたい歯だけを的確にコントロールできます。
また、成人矯正のように歯の動きがゆるやかになりがちな方や、治療期間をできるだけ短くしたい方にも適しています。
矯正中の見た目を気にする方にとっても、装置が目立たない点は大きな魅力です。
精度・スピード・審美性を重視したい方には、非常に相性の良い治療法といえるでしょう。
インプラント矯正が向いていない人
一方で、インプラント矯正が適さないケースもあります。
まず、成長期の子どもは原則として対象外です。
顎の骨がまだ発達途中にあるため、埋め込んだスクリューが成長とともに動いてしまう可能性があります。
また、歯を支えるあごの骨(歯槽骨)の厚みや硬さが十分でない方、歯周病や糖尿病などの全身疾患を抱える方も注意が必要です。
骨や歯ぐきの健康状態が安定していないと、スクリューの固定が難しく、炎症リスクが高まります。
喫煙習慣がある方も、血流の低下により傷の治りが遅れる場合があります。
このような場合は、まず歯周病治療や生活習慣の改善を行い、口腔環境を整えてから検討することが望ましいでしょう。
自分に合うかを見極めるポイント
インプラント矯正の適応は、歯科医師による正確な診断が不可欠です。
レントゲンやCTで骨の状態を確認し、スクリューを安全に設置できるかを判断します。
また、矯正のゴールや希望する仕上がりによっても、最適な方法は異なります。
たとえば「前歯の傾きを整えたい」「噛み合わせを改善したい」など、目的によってはワイヤー矯正やマウスピース矯正のほうが適している場合もあります。
近年では、インプラント矯正と他の矯正方法を組み合わせたコンビネーション治療も行われており、症例に応じて柔軟に選択することができます。
そのため、「どんな動きを目指すのか」「どんな見た目にしたいのか」を明確にしたうえで、歯科医師と相談することが成功への第一歩です。
7.インプラント矯正の治療期間と費用の目安

矯正治療を検討する際、多くの方が気になるのが「どのくらいの期間がかかるのか」「費用はいくらくらいなのか」という点です。
インプラント矯正は、治療の精度が高い分、計画性と技術力が求められます。
ここでは、一般的な治療期間や費用の目安、そしてその金額に影響する要素についてわかりやすく解説します。
あくまで一例として参考にし、自分の症例に合わせて歯科医師に相談することが大切です。
治療期間の目安と短縮の理由
インプラント矯正の治療期間は、症例によって差がありますが、おおよそ1年半〜2年程度が一般的です。
これは通常のワイヤー矯正と比べても短くなるケースが多く、歯の移動を効率的に行えることが理由です。
支点となる矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)が動かないため、狙った方向に確実に力を加えることができ、不要な歯の動きが起きにくくなります。
その結果、従来の矯正では2〜3年かかるケースでも、治療期間が数か月〜半年ほど短縮されることがあります。
また、スクリューを併用することで動きにくい奥歯の移動がスムーズになり、治療全体の進行も安定します。
ただし、歯の動きや骨の状態には個人差があるため、実際の期間は診断結果によって異なります。
費用の相場とその内訳
インプラント矯正は自由診療(保険適用外)で行われる治療です。
費用の相場は、スクリュー1本あたり数万円程度+通常の矯正治療費となります。
スクリューの埋入本数や使用箇所、併用する矯正方法(ワイヤー矯正・マウスピース矯正など)によっても総額は変わります。
たとえば、全体矯正の一部にインプラントを併用する場合は、装置代や管理費を含めて80万円〜120万円前後が目安となることが多いです。
また、部分的な矯正や短期的な治療に使用する場合は、より低い費用で行えることもあります。
費用はスクリューの本数・装置の種類・通院頻度・保定(歯並びを安定させる期間)・調整料などによって変動します。
歯科医院によって料金体系が異なるため、カウンセリング時に内訳を確認し、「どこに費用がかかるのか」を理解した上で納得して治療を始めることが重要です。
費用・期間を左右する要素
治療の費用や期間は、使用する装置の種類やスクリューの位置だけでなく、患者様の歯や骨の状態、生活習慣によっても変わります。
たとえば、骨がしっかりしている方はスクリューが安定しやすく、予定通りのスピードで歯が動く傾向があります。
一方で、骨が薄い、喫煙習慣がある、歯周病があるといった場合には、治療が慎重に進められることもあります。
また、矯正装置の調整間隔や通院頻度、治療後の保定装置(歯並びの後戻りを防ぐための装置)も
全体のスケジュールに影響します。
費用に関しては、医院ごとのメンテナンス料金や再調整費用なども確認しておくと安心です。
「どのくらいで終わるのか」「どれくらいの予算が必要か」を明確にした上で、自分に合った治療計画を立てることが成功への第一歩といえます。
8.インプラント矯正中・治療後のケアとメンテナンス

インプラント矯正を成功させるためには、スクリューを安定して維持し、口の中を清潔に保つことが欠かせません。
治療中のケアを怠ると、炎症や脱落などのトラブルにつながることもあります。
また、矯正が終わった後も歯の位置を安定させるための保定期間(歯並びを戻らないように固定する期間)がとても大切です。
ここでは、インプラント矯正中の正しいケア方法と、治療後に行うメンテナンスのポイントを紹介します。
スクリュー周囲の清掃と感染予防
インプラント矯正中に最も注意が必要なのが、スクリュー周囲の清掃です。
スクリューのまわりは食べかすやプラークが溜まりやすく、放置すると歯ぐきの炎症を引き起こすことがあります。
歯科医師から指導された方法で、やわらかめの歯ブラシやタフトブラシを使い、スクリューの根元まで丁寧に磨きましょう。
強くこすりすぎず、優しく円を描くように動かすのがポイントです。
また、抗菌作用のある洗口液を併用すると、より清潔な状態を保てます。
ブラッシングが不十分だとスクリューが緩む原因にもなるため、毎日のケアを習慣づけることが重要です。
炎症や出血がある場合は自己判断せず、早めに歯科医院に相談するようにしましょう。
治療中の生活と食事の注意点
インプラント矯正中は、スクリューが安定するまでの数日間に特に注意が必要です。
埋入直後は強い力が加わらないよう、硬い食べ物(フランスパン・ナッツなど)は避け、柔らかい食事を意識しましょう。
スクリューの周囲に違和感があっても、触ったり押したりしないようにします。
また、矯正装置とスクリューの間に食べ物が挟まりやすいため、食後のうがいをこまめに行うことも大切です。
清掃を怠ると細菌が繁殖し、炎症や口臭の原因となります。
定期的なメンテナンスでは、スクリューの緩みや周囲の清潔状態をチェックし、必要に応じて清掃や調整を行います。
普段通りの生活は可能ですが、「清潔・慎重・継続的」なケアを意識することが成功のカギです。
治療後のスクリュー除去と保定ケア
矯正治療が完了したら、スクリューを取り外す処置を行います。
除去は短時間で終わり、麻酔が不要な場合も多く、痛みもほとんどありません。
取り外し後の傷口は自然に閉じ、数日で治癒します。
しかし、ここで安心してケアを怠ると、せっかく整えた歯並びが後戻りしてしまうことがあります。
そのため、治療後は保定装置(リテーナー)を装着し、歯の位置を安定させる期間が設けられます。
保定期間はおおむね1〜2年程度が目安で、歯科医院で定期的にチェックを受けながら経過を見守ります。
また、保定期間中もブラッシングやフロス、洗口液などによる口腔ケアを継続することが大切です。
インプラント矯正は治療後の管理を丁寧に行うことで、きれいな歯並びを長く維持できる治療法といえます。
9.他の矯正方法との比較(ワイヤー矯正・マウスピース矯正など)

矯正治療にはさまざまな方法がありますが、それぞれに特徴と得意分野があります。
インプラント矯正は、他の矯正法と比べて「動かしたい歯を正確に動かせる」という強みがありますが、
ワイヤー矯正やマウスピース矯正(インビザライン)にもそれぞれの魅力があります。
ここでは、それぞれの矯正法の特徴や違いを比較しながら、どんなケースに向いているのかを詳しく見ていきましょう。
ワイヤー矯正との違い
ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケット(小さな金属またはセラミック製の装置)を装着し、
ワイヤーの力で歯を少しずつ動かしていく方法です。
もっとも歴史があり、幅広い症例に対応できる点が特徴です。
一方で、ワイヤー矯正では動かしたい歯と支点となる歯が引っ張り合うため、
奥歯をうしろ側へ動かす(後方移動)ような複雑な動きは時間がかかる傾向があります。
そこで、矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)を用いたインプラント矯正を併用すると、
動かしたくない歯を支点にせず、スクリューを固定源としてピンポイントで歯を移動させることができます。
つまり、ワイヤー矯正の「動かす力」とインプラント矯正の「固定力」を組み合わせることで、
より精密で計画的な治療が可能になります。
そのため、両者を併用した治療は、実際の臨床でも非常に多く採用されています。
ワイヤー矯正について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
マウスピース矯正(インビザライン)との違い
マウスピース矯正(代表的なものはインビザライン)は、透明で取り外し可能なマウスピースを使って歯を動かす方法です。
見た目に目立たず、装着時の違和感が少ないため、近年人気が高まっています。
ただし、マウスピース矯正は力の方向や強さに制限があるため、
大きく歯を動かす症例や、奥歯を後方に移動させるケースでは十分な効果を得にくい場合があります。
そのような難症例では、インプラント矯正を併用することで、
マウスピースだけでは得にくい力のかけ方を補い、治療の安定性と精度を高めることができます。
このように、インビザラインとインプラント矯正を組み合わせた「ハイブリッド矯正」は、
見た目の自然さと治療効果を両立できる方法として注目されています。
インビザラインについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
自分に合った治療法を選ぶために
矯正治療を成功させるためには、「自分の歯並びと生活スタイルに合った方法を選ぶこと」が何より重要です。
たとえば、仕事や学校で装置の見た目を気にする方にはマウスピース矯正が適しています。
一方で、短期間でしっかり歯を動かしたい方、奥歯を後方に移動させたい方には、
インプラント矯正を併用した治療が効果的です。
ワイヤー矯正・マウスピース矯正・インプラント矯正は、それぞれ得意分野が異なります。
最近では、これらを組み合わせて一人ひとりの症例に合わせたオーダーメイド治療を行う歯科医院も増えています。
「どの治療法が自分に合うか」ではなく、「どの組み合わせがベストか」を専門医と相談することが、最良の結果への近道です。
10.自分に合った矯正を選ぶために:インプラント矯正からインビザラインへ

歯並びの悩みや希望は、人それぞれ異なります。
「短期間で整えたい」「目立たずに矯正したい」「噛み合わせまでしっかり治したい」――。
インプラント矯正は精密な治療が可能な一方で、見た目の自然さを重視する方にはマウスピース矯正(インビザライン)も人気があります。
ここでは、両者の特性を活かしながら自分に合った矯正を選ぶための考え方を解説します。
治療選びのヒントとしてお役立てください。
精密さを求めるならインプラント矯正
インプラント矯正は、「力のコントロールが難しい症例」や「大きな歯の移動が必要な症例」に向いています。
矯正用の小さなネジ(アンカースクリュー)を固定源として使うことで、動かしたい歯を狙った方向へ正確に導くことができます。
たとえば、奥歯をうしろ側へ動かす(後方移動)や、前歯を引き下げるといった複雑な動きも可能です。
このため、従来の矯正では時間がかかった症例でも、治療期間を短縮できる場合があります。
また、スクリューは口腔内で目立たず、装置を最小限にできるため、見た目のストレスも少ないのが特徴です。
「精密性」「スピード」「安定性」の3つを重視する方にとって、インプラント矯正は非常に適した選択肢といえるでしょう。
ただし、骨や歯ぐきの状態によっては適応が難しい場合もあるため、専門医による診断が欠かせません。
目立たず快適に治したいならインビザライン
一方、インビザラインは「人に気づかれずに矯正したい」「取り外して清潔に保ちたい」という方に向いています。
透明なマウスピースを段階的に交換しながら歯を少しずつ動かしていくため、装着中も自然な見た目です。
食事や歯みがきの際には取り外せるため、清掃がしやすく、虫歯や歯ぐきの炎症を防ぎやすい点も大きな利点です。
また、装置による痛みや口内炎が起こりにくく、発音や食事への影響も少ないため、
仕事中や人と話す機会の多い方にも支持されています。
ただし、マウスピース矯正は患者様自身の装着時間(1日20時間以上)が結果に影響するため、自己管理が重要です。
「快適さ」「審美性」「ライフスタイルの柔軟性」を重視する方には、インビザラインが最適です。
インプラント矯正とインビザラインの組み合わせという選択
最近では、インプラント矯正とインビザラインを併用する「コンビネーション矯正」も注目されています。
インプラント矯正の固定力を利用して歯を正確に動かしながら、
見た目には透明なマウスピースを使用することで、精密さと審美性の両立が可能になります。
たとえば、奥歯の後方移動にインプラント矯正を用い、その後の全体的な歯列調整をインビザラインで行うケースなど、
症例に合わせて柔軟に対応できるのが特徴です。
こうしたハイブリッド治療は、専門的な診断力と技術を持つ歯科医院で行われることが多く、
「見た目・効果・快適さ」の3要素をバランスよく満たした治療法といえます。
自分の希望やライフスタイルに合わせて、最適な治療法を提案してくれる歯科医院を選ぶことが大切です。
まずはお気軽にご相談ください
神奈川県伊勢原市の
見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)
『 つじむら歯科医院 伊勢原 』
住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1
TEL:0463-95-8214
【監修者情報】
つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑
【略歴】
1993年 神奈川歯科大学 卒業
1995年 つじむら歯科医院 開業
1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設
2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院
2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了
2010年 南カリフォルニア大学客員研究員
2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)
2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業
2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了
2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師
2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医
2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任
2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長
【所属】
IIPD国際予防歯科学会認定医
日本抗加齢医学会認定医
日本歯科人間ドック学会認定医
日本口腔医学会認定医
セカンドオピニオン専門医
DGZI国際インプラント学会認定医
日本咀嚼学会会員
日本保存学会会員
日本全身咬合学会会員
日本口腔インプラント学会会員
国際歯周内科学研究会会員
日本口腔内科学研究会会員
日本床矯正研究会会員
神奈川矯正研究会会員
日本臨床唾液学会会員
NPO法人歯と健康を守ろう会会員
日本ヘルスケア歯科研究会会員
伊勢原市中央保育園学校歯科医
日本食育指導士
健康咀嚼指導士